ロング・タイム・アゴー。@大江山花伝
2009年8月12日 タカラヅカ 木原敏江を知ったのは、タカラヅカがきっかけだ。
年に1回くらいかな、母に連れられて観劇していたんだ、あのころ。
その日思い立って出かけるもんだから、演目は知らない。「タカラヅカ」というブランドに信頼があるので、出演者も演出家も演目も知らずに出かける。「あの店に行けば、おいしいものが食べられる」くらいの感覚で。
演目は『青き薔薇の軍神』だった。『アンジェリク』という作品の続編らしい。さすが続編、なんかよくわかんなかった(笑)。や、わたしはアタマの悪いガキだったので。
そのときの幕間に抽選によるプレゼント企画があって。
景品はいろいろあったと思うけど、よくおぼえてない。わたしが痛烈に記憶に残しているのは、その中に「原作本」があったことだけ。
というのも、わたしの隣の席の人が当たったのよ、原作本が。
さもしいガキだったので、1番違いで原作マンガ本が当たらなかったことが、ことのほかくやしかった。残念だった。
だってマンガ本のプレゼントなんて、他ではなかなかない機会ですよ。マンガ大好きなのに、ジャンル問わずなんでも読みたいし欲しいのに。
1番違いなら当たっていたのに……あのマンガはわたしのものだったのに……当日券だから、ほんとにちょっとした運の差ではずれちゃったんだ。
くやしさを抱えたまま後日、近所の書店で『アンジェリク』を見つけた。小さな「町の本屋さん」のささやかなマンガ本コーナーに、1冊だけあった。
これだ、あのお芝居の原作本。わたしがもらえなかったやつ!←しつこい
モノを考えないガキだったので、そこで見つけた1冊を買った。ちなみに、4巻。
いきなり、4巻。
1巻から4巻まで買ったのではなく、4巻1冊だけ。や、だって、4巻1冊しか売ってなかったんだってば、その本屋さん。
今ならありえない、そんな買い方。全5巻のマンガ本を、4巻だけ買ってどーするんだ。
でもそのころのわたしはなーんも考えず、「お芝居観たし、途中からでもわかるだろー」と思っていた。
まあ実際、『青き薔薇の軍神』は4巻あたりの話だったので、途中から読んでもなんとなくわかった。
そのあと5巻を買って完結したから納得。当時のわたしにマンガを一気買いする甲斐性などあるはずもなく、おこづかいからちまちま1冊ずつしか買えなかったんだな。
1~3巻を買って読んだのは、それからずーっとあと、おこづかいに余裕が出来てからだ。
なんなの、その変な読み方。「物語」への冒涜だわ。
4巻だけとか、4巻と5巻だけだと感想は「ふーん?」程度だった。そりゃそーだよな、途中からでストーリーわかってないし、キャラに愛着もないし。
でも、1巻から順番に、ちゃんと読んだらおもしろかったんだよ、『アンジェリク』! 当たり前だけど!
「物語」は正しく読もう! 教訓ですよ。深くモノを考えず、よりによって『異邦の騎士』を最初に読んじゃって、本好き友人たちから「なんでそんなアホな読み方したんだ」と憐れみの目で見られたりした、そーゆー人間ですよわたしは。順番に読まなきゃダメだよ、「物語」は!(脱線してます)
とにかく。(話を戻す)
それから、木原敏江作品を読むようになった。
だから、はじまりはタカラヅカ。
あのときふらりとヅカに行っていなければ、木原敏江を知ることはなかった。
『大江山花伝』も、先に原作を読んでいた。
『青き薔薇の軍神』は舞台が先だったし、アホなわたしはナニがなんだかわかっていなかった。しかし『大江山花伝』は、原作が先。すでに原作者のファン。その状態で、舞台を見て。
首を、傾げた。
あれえ? なんか、思っていたのと、チガウ。
わたしが原作から受けていたイメージと、舞台はまったくちがっていた。
今よりもっとアタマのゆるい子だったわたしは、深くは考えなかったけれどその違和感を、なんか、苛っとすると、思った。
言葉にして、組み立てて考えることはできなかったけれど、原作ファンとして、引っかかりを感じた。
それは、植爺作の『ベルサイユのばら』をはじめて観たときに感じたモノと似ていた。
だから、「マンガが舞台化されるときに、感じること」なんだろうと、当時のわたしは結論づけていた、と思う。
マンガがそのまま舞台になるわけじゃない、そんなことは不可能だから、そこに違和感を持つのだろう、と。
植爺の『ベルばら』だって、最後に泣かせてくれるから(当時はアレで大泣きしていた)感動の名作だと思っていた。
それと同じように、柴田せんせの『大江山花伝』も、最後に泣かせてくれるから、感動の名作だと思った。
どちらの作品も、観ていて苛っとしたんだけどね。
チガウだろコレ、と、思ったんだけどね。
当時のわたしは、深くは考えられなかった。
『大江山花伝』に感じた違和感の、いちばん大きなモノは、鬼の描き方だった。
チガウだろ? ソレってありえないだろ?! と、当時のわたしですら、思った(笑)。
原作の鬼はあんなんじゃないー、このトホホ感はなんなの。こんなにダサくしないと舞台って成り立たないの?
『ベルばら』の悶絶夫人や失神夫人と同じ臭いを感じたんだ。だから、タカラヅカの舞台には必要なことなのかと思った。
あとは妙な説教臭さに辟易とした。
語りすぎると、美しさが損なわれる。
でもそれもまた『ベルばら』と同じ臭いだったので、これもまたタカラヅカなんだと以下略。
衣装やセットは豪華だけれど、耽美ではない。耽美ってのは、こんな下世話で悪趣味なものではない。
でもそれもまた『ベルばら』と同じ臭いだったので、これもまたタカラヅカなんだと以下略。
ヅカファンではなく、タカラヅカもたまに観るマンガファンでしかないわけだから、「そーゆーもんなんだ」と受け入れて終了。
どーせヅカなんて年に1回、観るか観ないか、誰がトップスターなのかも知らない状態。
多くは求めていない。
今思えば、あの苛っとした感じ、違和感は、大衆演劇のかほりだったのかなと思う。
マンガを読む能力のない年配者(コマを追うことができないらしい)にも、物語をわかりやすく説明しなければならない、「余計なお世話」的な部分が鼻についたのだと思う。台詞だけの問題ではなく、表現自体のうっとーしさは。
行間を読むことなどない、1から10まで説明してわかりやすく、老若男女どんな人でもついてこられる作品であることを宿命づけられた「大劇場作品」であるゆえの鈍くささ。
植爺にしろ柴田せんせにしろ、宝塚歌劇団の座付き作家として正しく任を果たしている人たちだ。
そしてそれは、現代では「古くさい」ということになる。
21世紀になって9年経つ現代では、タカラヅカも「昭和の大衆演劇」ではなくなっている。伝統は受け継いでいるが、スターのお化粧が昭和時代とは変わっているように、芝居も現代風になっている。
木原敏江のマンガも、決して現代風ではないけれど、それでも現代に独自の位置を確立している。
タカラヅカだけが古いまま、昭和のまま再演する現実に、ちょっと苦笑しつつ、それすら受け入れて、あきらめて、博多座へ行った。
覚悟していたので、それほど作品に辟易とはしなかった。
あの、なにも考えていなかった当時ですら引っかかった作品だもの、今観てつらくないはずがない、と。
センスに相容れないモノはあるにせよ、ベストではなくベターで満足しなければヅカファンなんてやってられない、大丈夫、よいお披露目作品だった。
でももう、再演はしないでね(笑)、脚本・演出を別の人が1からしない限り。(植爺の『ベルばら』と同じ)
年に1回くらいかな、母に連れられて観劇していたんだ、あのころ。
その日思い立って出かけるもんだから、演目は知らない。「タカラヅカ」というブランドに信頼があるので、出演者も演出家も演目も知らずに出かける。「あの店に行けば、おいしいものが食べられる」くらいの感覚で。
演目は『青き薔薇の軍神』だった。『アンジェリク』という作品の続編らしい。さすが続編、なんかよくわかんなかった(笑)。や、わたしはアタマの悪いガキだったので。
そのときの幕間に抽選によるプレゼント企画があって。
景品はいろいろあったと思うけど、よくおぼえてない。わたしが痛烈に記憶に残しているのは、その中に「原作本」があったことだけ。
というのも、わたしの隣の席の人が当たったのよ、原作本が。
さもしいガキだったので、1番違いで原作マンガ本が当たらなかったことが、ことのほかくやしかった。残念だった。
だってマンガ本のプレゼントなんて、他ではなかなかない機会ですよ。マンガ大好きなのに、ジャンル問わずなんでも読みたいし欲しいのに。
1番違いなら当たっていたのに……あのマンガはわたしのものだったのに……当日券だから、ほんとにちょっとした運の差ではずれちゃったんだ。
くやしさを抱えたまま後日、近所の書店で『アンジェリク』を見つけた。小さな「町の本屋さん」のささやかなマンガ本コーナーに、1冊だけあった。
これだ、あのお芝居の原作本。わたしがもらえなかったやつ!←しつこい
モノを考えないガキだったので、そこで見つけた1冊を買った。ちなみに、4巻。
いきなり、4巻。
1巻から4巻まで買ったのではなく、4巻1冊だけ。や、だって、4巻1冊しか売ってなかったんだってば、その本屋さん。
今ならありえない、そんな買い方。全5巻のマンガ本を、4巻だけ買ってどーするんだ。
でもそのころのわたしはなーんも考えず、「お芝居観たし、途中からでもわかるだろー」と思っていた。
まあ実際、『青き薔薇の軍神』は4巻あたりの話だったので、途中から読んでもなんとなくわかった。
そのあと5巻を買って完結したから納得。当時のわたしにマンガを一気買いする甲斐性などあるはずもなく、おこづかいからちまちま1冊ずつしか買えなかったんだな。
1~3巻を買って読んだのは、それからずーっとあと、おこづかいに余裕が出来てからだ。
なんなの、その変な読み方。「物語」への冒涜だわ。
4巻だけとか、4巻と5巻だけだと感想は「ふーん?」程度だった。そりゃそーだよな、途中からでストーリーわかってないし、キャラに愛着もないし。
でも、1巻から順番に、ちゃんと読んだらおもしろかったんだよ、『アンジェリク』! 当たり前だけど!
「物語」は正しく読もう! 教訓ですよ。深くモノを考えず、よりによって『異邦の騎士』を最初に読んじゃって、本好き友人たちから「なんでそんなアホな読み方したんだ」と憐れみの目で見られたりした、そーゆー人間ですよわたしは。順番に読まなきゃダメだよ、「物語」は!(脱線してます)
とにかく。(話を戻す)
それから、木原敏江作品を読むようになった。
だから、はじまりはタカラヅカ。
あのときふらりとヅカに行っていなければ、木原敏江を知ることはなかった。
『大江山花伝』も、先に原作を読んでいた。
『青き薔薇の軍神』は舞台が先だったし、アホなわたしはナニがなんだかわかっていなかった。しかし『大江山花伝』は、原作が先。すでに原作者のファン。その状態で、舞台を見て。
首を、傾げた。
あれえ? なんか、思っていたのと、チガウ。
わたしが原作から受けていたイメージと、舞台はまったくちがっていた。
今よりもっとアタマのゆるい子だったわたしは、深くは考えなかったけれどその違和感を、なんか、苛っとすると、思った。
言葉にして、組み立てて考えることはできなかったけれど、原作ファンとして、引っかかりを感じた。
それは、植爺作の『ベルサイユのばら』をはじめて観たときに感じたモノと似ていた。
だから、「マンガが舞台化されるときに、感じること」なんだろうと、当時のわたしは結論づけていた、と思う。
マンガがそのまま舞台になるわけじゃない、そんなことは不可能だから、そこに違和感を持つのだろう、と。
植爺の『ベルばら』だって、最後に泣かせてくれるから(当時はアレで大泣きしていた)感動の名作だと思っていた。
それと同じように、柴田せんせの『大江山花伝』も、最後に泣かせてくれるから、感動の名作だと思った。
どちらの作品も、観ていて苛っとしたんだけどね。
チガウだろコレ、と、思ったんだけどね。
当時のわたしは、深くは考えられなかった。
『大江山花伝』に感じた違和感の、いちばん大きなモノは、鬼の描き方だった。
チガウだろ? ソレってありえないだろ?! と、当時のわたしですら、思った(笑)。
原作の鬼はあんなんじゃないー、このトホホ感はなんなの。こんなにダサくしないと舞台って成り立たないの?
『ベルばら』の悶絶夫人や失神夫人と同じ臭いを感じたんだ。だから、タカラヅカの舞台には必要なことなのかと思った。
あとは妙な説教臭さに辟易とした。
語りすぎると、美しさが損なわれる。
でもそれもまた『ベルばら』と同じ臭いだったので、これもまたタカラヅカなんだと以下略。
衣装やセットは豪華だけれど、耽美ではない。耽美ってのは、こんな下世話で悪趣味なものではない。
でもそれもまた『ベルばら』と同じ臭いだったので、これもまたタカラヅカなんだと以下略。
ヅカファンではなく、タカラヅカもたまに観るマンガファンでしかないわけだから、「そーゆーもんなんだ」と受け入れて終了。
どーせヅカなんて年に1回、観るか観ないか、誰がトップスターなのかも知らない状態。
多くは求めていない。
今思えば、あの苛っとした感じ、違和感は、大衆演劇のかほりだったのかなと思う。
マンガを読む能力のない年配者(コマを追うことができないらしい)にも、物語をわかりやすく説明しなければならない、「余計なお世話」的な部分が鼻についたのだと思う。台詞だけの問題ではなく、表現自体のうっとーしさは。
行間を読むことなどない、1から10まで説明してわかりやすく、老若男女どんな人でもついてこられる作品であることを宿命づけられた「大劇場作品」であるゆえの鈍くささ。
植爺にしろ柴田せんせにしろ、宝塚歌劇団の座付き作家として正しく任を果たしている人たちだ。
そしてそれは、現代では「古くさい」ということになる。
21世紀になって9年経つ現代では、タカラヅカも「昭和の大衆演劇」ではなくなっている。伝統は受け継いでいるが、スターのお化粧が昭和時代とは変わっているように、芝居も現代風になっている。
木原敏江のマンガも、決して現代風ではないけれど、それでも現代に独自の位置を確立している。
タカラヅカだけが古いまま、昭和のまま再演する現実に、ちょっと苦笑しつつ、それすら受け入れて、あきらめて、博多座へ行った。
覚悟していたので、それほど作品に辟易とはしなかった。
あの、なにも考えていなかった当時ですら引っかかった作品だもの、今観てつらくないはずがない、と。
センスに相容れないモノはあるにせよ、ベストではなくベターで満足しなければヅカファンなんてやってられない、大丈夫、よいお披露目作品だった。
でももう、再演はしないでね(笑)、脚本・演出を別の人が1からしない限り。(植爺の『ベルばら』と同じ)
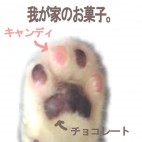
コメント