巴里のまっつ・その3。@宝塚巴里祭2009
2009年7月12日 タカラヅカ まっつが登場すると、途端雰囲気が変わる。
下級生たち=明るくさわやかに、まっつ=重厚に、というコンセプトなのか。や、逆だったらいたたまれないので(笑)、これで十分ですが。
「夜霧のモンマルトル」から、そのまま「黒い鷲」に移る。
曲が変わると、まっつも変わる。
重厚かつクラシカルだった「夜霧の~」から、「黒い鷲」スタートと共に、まっつになにかスイッチが入る。
それまでは「歌」であり、「ディナーショー」だった気がする。
そこから、別のところへシフトチェンジする。
「黒い鷲」を歌いはじめたまっつが、どれほどこの曲を、ことばを、大切にしているかが伝わってきた。なにかやわらかい、はかないものを抱えているような。
腕の中のはかないものを、あやすように揺らしながら歌っているというか。
それは小さな灯火で、強い光の中では見えない。
だけどたしかに、在る。
歌声は力となり、はかない灯火は徐々に広がっていく。
「歌」は歌であるに留まらず、そこに「物語」を紡ぎ出す。
クリアに届く歌詞、「伝える」という基本を押さえた明瞭な声。
まっつの歌はいつも「巧い」けれど、感情を伝えるのは苦手だと思う。彼の歌の巧さ、正しい音程やリズム、滑舌ほどに、情感や表現が届いていない感じ。
それは一朝一夕でどうなるものでもないんだろう。
この「黒い鷲」も、歌だけで感情を表現し切れていたかは、あやしい。
だけどまっつは、表現しようとしていた。
大切に大切に、歌……「作品」と向き合い、真っ向から挑んでいた。
感情をのせるために、まっつはまっつのすべてを使っていたと思う。
声、歌だけでなく、カラダすべて。持てるものすべて。
だからこそ。
歌からダンスに移ったときに、涙腺が決壊した。
まっつは歌の人だとカテゴライズされがちだけれど、十分踊れる人だとも思っている。
わたしはダンスの善し悪しがわかっていない人間なんで、説得力ナイっちゃーナイんだが。
それでも、思った。
めぐむとるなくんを両脇に、センターで踊るまっつを見て。
この人は、タカラヅカだ。
かなしいほど、思った。痛感した。
この人は、「タカラヅカ」だ。
95年続いてきた、この奇異な文化、長い年月とたくさんの人々の手を経て磨かれ淘汰され研ぎ澄まされてきた、その「型」を美しくプリミティヴに受け継いでいる。
現代の「タカラヅカ」はすでに小柄な男役を必要としていないのかもしれないが、時代がどうあれ、「タカラヅカ」としての技術を体現してみせる小さな背中に、感動と、喜びと、切なさを感じた。
この人は、「タカラヅカ」というファンタジーの、一面を具現しているひとりなんだ、と。
いびつで、ある意味滑稽で、だけど美しくて魅力的な、他にない他のナニかでは代え難い、「タカラヅカの男役」というもの。
だからこそ、こんなにこんなに、好きなんだ。
受け継がれてきた美しさ。時代の変化に消されることなく、どんだけ奇異な世界であろうと、それを愛する人から人へ伝えられ、生き残ってきた。
その、美しさだ。
その、型だ。
ひとの想いがつらなり、力となり、ここに至るんだ。
それを感じた。
踊るまっつを見て。
まっつはまぎれもなく「タカラヅカ」で、泣けるほど「タカラヅカ」で、そして、「花組」だ。
「タカラヅカ」の、「花組」の遺伝子を持ち、ここにいる。
「黒い鷲」までは、「歌」であり、「ディナーショー」だった。
だがこの曲で、「歌」でも「ディナーショー」でもなく、別のモノになった。
「舞台」になった。
「芝居」でも「ダンス」でもなく。
それらすべてを内包する、表現する、「舞台」になった。「タカラヅカ」になった。
確かめるように確実に踊り、舞い降りたまっつは、またひとり歌い出す。
夢のように。
歌声だけでは、足りないかもしれない。まっつは端正に歌うことは得意でも、饒舌に歌うことは苦手だ。でもたしかに今、まっつは表現した。「黒い鷲」という曲を。
まっつの持つ、すべてで。
『宝塚巴里祭2009』7月9日の「黒い鷲」は、とんでもなかった。
鳥肌が立つ、血の気が引く……と、なんか悪い感じの表現になるが、そんな感覚を味わうのは、久しぶりだ。
精神的な衝撃から、自分の身体が変化し、その変化にカラダが悲鳴を上げているのがわかる。体温が上昇し、足りない血を補うために心臓が早鐘を打つのがわかる。
こりゃ貧血来るな、と思った。「作品」を見て貧血起こすのって、『アルバトロス、南へ』の青年館初日以来?
『宝塚巴里祭2009』のクライマックスが終了、次はフィナーレになる。
「Laissez-moi danser」は若者たちで、だよね? なんかもお、記憶が怪しすぎる。
油断しているところで、後ろのお立ち台にまっつ登場、それまでを吹き飛ばすように明るくラストを飾る。
プログラムにある最後の曲は「ラビアン・ローズ」。
曲にのせて最後の挨拶したり、みんなでノリノリに終了。
えーと、客席降りが何回かあり、そのたびにまっつは一本釣りしまくりで場内おおさわぎだったんだが、どこでどうだったかわかんねー。
下級生たちもいっぱい降りてきてくれて、華やかで楽しかった。
9日は、初日よりさらにうしろの席だったので、客席降りだろーと舞台だろーと、いつもまっつは遠く、お立ち台にいるときがいちばん近いかなってなロケーションだった。
客席降りしているまっつを見るために、オペラグラスのぞくぐらいには、いつも遠かった(笑)。
でも、落ち着く。
まっつをオペラでガン見していると、「いつものわたし」って感じで(笑)。
そーやって平静を取り戻そうとしていたのに、最後の最後、舞台に戻るためにわたしの横を走り抜けてくまっつとちらりと目が合って、またわたし的に「どっかん」なキモチになったしな。同じテーブルの友人たちに、目線もらって反応しまくっていたことを、初日に続いて指摘されるしな。あああ。
プログラムにない、本当の最後の1曲「愛の讃歌」。
寿美礼サマの豪華衣装(だよな?)に身を包み、熱唱するまっつ。よりによってこの衣装か(笑)。
初日はこの曲がいちばん素晴らしかったが、翌日は「黒い鷲」がすごすぎてこちらはふつうに美しい良い歌声として聴いた。別に、歌声が劣っていたわけではないから、「黒い鷲」がえーらいこっちゃ、だっただけだよな。
終わったあと、興奮さながらに立ち上がって拍手している人がいたが、他に誰も立たないのであわてて坐ってたり、これからも拍手が続きそうなのに、拍手が続けばスタンディングもなくはなさそうなのに、まっつがばっさりと「気を付けてお帰り下さい」と終わらせたりで、その余韻のぶった切り方に、かえってウケる。
いやあ、容赦なくまっつ!って感じ(笑)。
誰かわたしに記憶を下さい。
優秀な海馬を下さい。
留めたくてあがくのに、文字にしたい、残したいと切望するのに、まったく思うようにならない。
うおお、まっつまっつまっつ。
下級生たち=明るくさわやかに、まっつ=重厚に、というコンセプトなのか。や、逆だったらいたたまれないので(笑)、これで十分ですが。
「夜霧のモンマルトル」から、そのまま「黒い鷲」に移る。
曲が変わると、まっつも変わる。
重厚かつクラシカルだった「夜霧の~」から、「黒い鷲」スタートと共に、まっつになにかスイッチが入る。
それまでは「歌」であり、「ディナーショー」だった気がする。
そこから、別のところへシフトチェンジする。
「黒い鷲」を歌いはじめたまっつが、どれほどこの曲を、ことばを、大切にしているかが伝わってきた。なにかやわらかい、はかないものを抱えているような。
腕の中のはかないものを、あやすように揺らしながら歌っているというか。
それは小さな灯火で、強い光の中では見えない。
だけどたしかに、在る。
歌声は力となり、はかない灯火は徐々に広がっていく。
「歌」は歌であるに留まらず、そこに「物語」を紡ぎ出す。
クリアに届く歌詞、「伝える」という基本を押さえた明瞭な声。
まっつの歌はいつも「巧い」けれど、感情を伝えるのは苦手だと思う。彼の歌の巧さ、正しい音程やリズム、滑舌ほどに、情感や表現が届いていない感じ。
それは一朝一夕でどうなるものでもないんだろう。
この「黒い鷲」も、歌だけで感情を表現し切れていたかは、あやしい。
だけどまっつは、表現しようとしていた。
大切に大切に、歌……「作品」と向き合い、真っ向から挑んでいた。
感情をのせるために、まっつはまっつのすべてを使っていたと思う。
声、歌だけでなく、カラダすべて。持てるものすべて。
だからこそ。
歌からダンスに移ったときに、涙腺が決壊した。
まっつは歌の人だとカテゴライズされがちだけれど、十分踊れる人だとも思っている。
わたしはダンスの善し悪しがわかっていない人間なんで、説得力ナイっちゃーナイんだが。
それでも、思った。
めぐむとるなくんを両脇に、センターで踊るまっつを見て。
この人は、タカラヅカだ。
かなしいほど、思った。痛感した。
この人は、「タカラヅカ」だ。
95年続いてきた、この奇異な文化、長い年月とたくさんの人々の手を経て磨かれ淘汰され研ぎ澄まされてきた、その「型」を美しくプリミティヴに受け継いでいる。
現代の「タカラヅカ」はすでに小柄な男役を必要としていないのかもしれないが、時代がどうあれ、「タカラヅカ」としての技術を体現してみせる小さな背中に、感動と、喜びと、切なさを感じた。
この人は、「タカラヅカ」というファンタジーの、一面を具現しているひとりなんだ、と。
いびつで、ある意味滑稽で、だけど美しくて魅力的な、他にない他のナニかでは代え難い、「タカラヅカの男役」というもの。
だからこそ、こんなにこんなに、好きなんだ。
受け継がれてきた美しさ。時代の変化に消されることなく、どんだけ奇異な世界であろうと、それを愛する人から人へ伝えられ、生き残ってきた。
その、美しさだ。
その、型だ。
ひとの想いがつらなり、力となり、ここに至るんだ。
それを感じた。
踊るまっつを見て。
まっつはまぎれもなく「タカラヅカ」で、泣けるほど「タカラヅカ」で、そして、「花組」だ。
「タカラヅカ」の、「花組」の遺伝子を持ち、ここにいる。
「黒い鷲」までは、「歌」であり、「ディナーショー」だった。
だがこの曲で、「歌」でも「ディナーショー」でもなく、別のモノになった。
「舞台」になった。
「芝居」でも「ダンス」でもなく。
それらすべてを内包する、表現する、「舞台」になった。「タカラヅカ」になった。
確かめるように確実に踊り、舞い降りたまっつは、またひとり歌い出す。
夢のように。
歌声だけでは、足りないかもしれない。まっつは端正に歌うことは得意でも、饒舌に歌うことは苦手だ。でもたしかに今、まっつは表現した。「黒い鷲」という曲を。
まっつの持つ、すべてで。
『宝塚巴里祭2009』7月9日の「黒い鷲」は、とんでもなかった。
鳥肌が立つ、血の気が引く……と、なんか悪い感じの表現になるが、そんな感覚を味わうのは、久しぶりだ。
精神的な衝撃から、自分の身体が変化し、その変化にカラダが悲鳴を上げているのがわかる。体温が上昇し、足りない血を補うために心臓が早鐘を打つのがわかる。
こりゃ貧血来るな、と思った。「作品」を見て貧血起こすのって、『アルバトロス、南へ』の青年館初日以来?
『宝塚巴里祭2009』のクライマックスが終了、次はフィナーレになる。
「Laissez-moi danser」は若者たちで、だよね? なんかもお、記憶が怪しすぎる。
油断しているところで、後ろのお立ち台にまっつ登場、それまでを吹き飛ばすように明るくラストを飾る。
プログラムにある最後の曲は「ラビアン・ローズ」。
曲にのせて最後の挨拶したり、みんなでノリノリに終了。
えーと、客席降りが何回かあり、そのたびにまっつは一本釣りしまくりで場内おおさわぎだったんだが、どこでどうだったかわかんねー。
下級生たちもいっぱい降りてきてくれて、華やかで楽しかった。
9日は、初日よりさらにうしろの席だったので、客席降りだろーと舞台だろーと、いつもまっつは遠く、お立ち台にいるときがいちばん近いかなってなロケーションだった。
客席降りしているまっつを見るために、オペラグラスのぞくぐらいには、いつも遠かった(笑)。
でも、落ち着く。
まっつをオペラでガン見していると、「いつものわたし」って感じで(笑)。
そーやって平静を取り戻そうとしていたのに、最後の最後、舞台に戻るためにわたしの横を走り抜けてくまっつとちらりと目が合って、またわたし的に「どっかん」なキモチになったしな。同じテーブルの友人たちに、目線もらって反応しまくっていたことを、初日に続いて指摘されるしな。あああ。
プログラムにない、本当の最後の1曲「愛の讃歌」。
寿美礼サマの豪華衣装(だよな?)に身を包み、熱唱するまっつ。よりによってこの衣装か(笑)。
初日はこの曲がいちばん素晴らしかったが、翌日は「黒い鷲」がすごすぎてこちらはふつうに美しい良い歌声として聴いた。別に、歌声が劣っていたわけではないから、「黒い鷲」がえーらいこっちゃ、だっただけだよな。
終わったあと、興奮さながらに立ち上がって拍手している人がいたが、他に誰も立たないのであわてて坐ってたり、これからも拍手が続きそうなのに、拍手が続けばスタンディングもなくはなさそうなのに、まっつがばっさりと「気を付けてお帰り下さい」と終わらせたりで、その余韻のぶった切り方に、かえってウケる。
いやあ、容赦なくまっつ!って感じ(笑)。
誰かわたしに記憶を下さい。
優秀な海馬を下さい。
留めたくてあがくのに、文字にしたい、残したいと切望するのに、まったく思うようにならない。
うおお、まっつまっつまっつ。
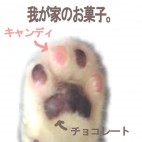
コメント