印刷技術の進歩、万歳!
これほど、「技術」の革新をよろこんだことがあったろうか。はじめてDVDレコーダを使ったときのような感動。最近で言うなら、買い直したDVDレコーダのW録画機能に震えるほど感動した(笑)、あのときのよーな思いだ。
ありがとう技術者の人たち!
と、幕開きから盛大によろこんだ。
今回の星組『ベルサイユのばらーフェルゼンとマリー・アントワネット編ー』のことだ。
つーのも、今回のプロローグは、「軽く3m×3mはあるだろーマンガの顔がぱかっと開いて、そこから役者が登場」という、最悪なパターンだったのね。演技で役を表現するとかじゃなく、マンガ絵まんま使ったプライドのカケラもないアレ。
このパターンを最初に観たときは、ショックだったなあ。
なにがショックって。
デッサンの狂い方が。
ありえねーだろ。
目の位置が変、鼻が変、口の位置はさらに変。……ふくわらい? 目隠ししてパーツを並べた? そうよね、そうでなきゃありえないわよね?
マンガ雑誌の「お便りコーナー」に載っている、「アタシ、マンガ描くの得意なの!」な中学生レベルの絵。
あまりに下手すぎる絵に、原作ファンとして顎が落ちた。
その汚すぎる絵から、アントワネットが、オスカルが、フェルゼンが出てくる絶望感。
お笑いじゃないんだからさ……シリアスで、悲劇なんだからさ……なんとか、もう少し……。
宝塚の舞台美術スタッフの技術の低さを思い知った瞬間(笑)。
そりゃ、わかるよ。数cmの小さな絵を同じサイズで写すのだって、手で模写する以上崩れるものだって。それをあの大きさにまで「手で」写すわけだから、マンガ絵を描いたことのない「素人」(舞台美術のプロでも、マンガ絵は素人だろ)にはあれが精一杯だったんだろう。
わたしの絶望は、そこじゃない。
少女マンガっちゅーのは独特の世界と計算式で成り立っている。もとの池田理代子の絵だって、「人体骨格的に正しい」絵ではない。だが、一定のルールと感性でデフォルメすることによってあのお目々きらきらの絵が成立しているんだ。
もしも「正しく」少女マンガを読める人があのグタグタに崩れたふくわらい絵を見たら、「おかしい。崩れてる」とわかるはずだ。考えるまでもなく。そして、そんなふーに「ふくわらい? もしくはピカソ?」ってくらい抽象的になってしまった絵を、金を取って何万人に見せるなんて、ふつーの神経をしていたらできない。
そこにあるのは、ただの「下手くそな絵」だ。プロの仕事ではなく、原作のルールを理解せずに描かれた「子どもの落書き」だ。
何故、プロの舞台関係者たちが、そんなひどいものを平気で商売に使うのか?
あのひどい絵を冒頭で見せられて、絶望したのはそこだ。
「この崩れた絵を平気で人目にさらすってことは、プロとしてのプライドを持たない人たちが、この舞台を作っているのではないか?」
……という危惧を通り越し、
「この崩れた絵を平気で人目にさらすってことは、崩れていることに、気づいてないのではないか?」
だったのよ。
前述の通り、原作の絵だって人体骨格的に正しいわけじゃない。それのみを正として見た場合、十分「崩れた、下手な絵」に見える。
少女マンガを理解できない人から見たら、原作のオスカルもアントワネットも、「子どもの落書き」ぐらい下手くそなまちがった絵なのよ。ルールに従ってデフォルメされているのに、そのルールを先天的に理解できない人から見たら、「ふくわらい?」くらい崩れた絵なの。
そーゆー人からみたら、原作の絵も、この舞台上のグダグダに崩れた絵も、どっちもどっち、どうせ崩れた変な絵でしかないってこと。
常識ではあり得ないくらい、崩れた絵が恥ずかしげもなく舞台で使われているこの現実は。
この絵が「崩れている」ことに気づかない人たちが、この舞台を作っている、ということ。
それはすなわち、
『ベルサイユのばら』を根本的に基本的に先天的に、理解できない人たちが、この舞台を作ったのではないか。
という絶望感だった。
そしてそれは、真実だった。
作・演出をする植田紳爾という人物は、最初から最後までついに『ベルサイユのばら』を理解できないままの人だった。
そう。
オープニングで、「これをオスカルと言ったら、オスカルへの冒涜だろ」という崩れた絵を使って平気であるということに象徴されたように。
てなことがあったから。
あれから何年? 何十年?
印刷技術は進歩し、マンガの小さな絵を、人間が手で大きく描き写す必要がなくなった。
原版をデジタル処理することによって、いくらでも、どんな加工でもできる時代になった。
もう映画館だって、似てない巨大な似顔絵看板を飾る必要はなくなった。宣伝用ポスター写真を拡大して看板にすればよい時代になった。
タカラヅカも、「素敵な絵ね」と言って、ヴィットリオ@オサとアンリエッタ@ふーちゃんの畳数枚サイズの写真を飾ることができるよーになった。
印刷技術の進歩、万歳!
これでもう、『ベルばら』のプロローグですでに絶望することもなくなった。
そこにあるのは、原作のイラストをまんま拡大したものだ。見慣れた絵だ。
植爺作品のひどさに、いずれ絶望するにしたって、幕が開くなり絶望、ということだけは回避された。
そこまで強く思わなくても、崩れたひどい絵を見て観客が失笑することはなくなった。……もちろん、マンガ絵を使うという演出のダサさに失笑がもれることがあったとしてもだ。
時の流れを感じたよ。
たかが、プロローグのマンガ絵1枚にね。
そして、そうやって印刷技術が変わって時代が変わったのに、それでも変わらない植爺のセンスと存在。
それに、感心し、改めて失笑した。
とゆー前振りではじめましょう、星組『ベルばら』の話。
これほど、「技術」の革新をよろこんだことがあったろうか。はじめてDVDレコーダを使ったときのような感動。最近で言うなら、買い直したDVDレコーダのW録画機能に震えるほど感動した(笑)、あのときのよーな思いだ。
ありがとう技術者の人たち!
と、幕開きから盛大によろこんだ。
今回の星組『ベルサイユのばらーフェルゼンとマリー・アントワネット編ー』のことだ。
つーのも、今回のプロローグは、「軽く3m×3mはあるだろーマンガの顔がぱかっと開いて、そこから役者が登場」という、最悪なパターンだったのね。演技で役を表現するとかじゃなく、マンガ絵まんま使ったプライドのカケラもないアレ。
このパターンを最初に観たときは、ショックだったなあ。
なにがショックって。
デッサンの狂い方が。
ありえねーだろ。
目の位置が変、鼻が変、口の位置はさらに変。……ふくわらい? 目隠ししてパーツを並べた? そうよね、そうでなきゃありえないわよね?
マンガ雑誌の「お便りコーナー」に載っている、「アタシ、マンガ描くの得意なの!」な中学生レベルの絵。
あまりに下手すぎる絵に、原作ファンとして顎が落ちた。
その汚すぎる絵から、アントワネットが、オスカルが、フェルゼンが出てくる絶望感。
お笑いじゃないんだからさ……シリアスで、悲劇なんだからさ……なんとか、もう少し……。
宝塚の舞台美術スタッフの技術の低さを思い知った瞬間(笑)。
そりゃ、わかるよ。数cmの小さな絵を同じサイズで写すのだって、手で模写する以上崩れるものだって。それをあの大きさにまで「手で」写すわけだから、マンガ絵を描いたことのない「素人」(舞台美術のプロでも、マンガ絵は素人だろ)にはあれが精一杯だったんだろう。
わたしの絶望は、そこじゃない。
少女マンガっちゅーのは独特の世界と計算式で成り立っている。もとの池田理代子の絵だって、「人体骨格的に正しい」絵ではない。だが、一定のルールと感性でデフォルメすることによってあのお目々きらきらの絵が成立しているんだ。
もしも「正しく」少女マンガを読める人があのグタグタに崩れたふくわらい絵を見たら、「おかしい。崩れてる」とわかるはずだ。考えるまでもなく。そして、そんなふーに「ふくわらい? もしくはピカソ?」ってくらい抽象的になってしまった絵を、金を取って何万人に見せるなんて、ふつーの神経をしていたらできない。
そこにあるのは、ただの「下手くそな絵」だ。プロの仕事ではなく、原作のルールを理解せずに描かれた「子どもの落書き」だ。
何故、プロの舞台関係者たちが、そんなひどいものを平気で商売に使うのか?
あのひどい絵を冒頭で見せられて、絶望したのはそこだ。
「この崩れた絵を平気で人目にさらすってことは、プロとしてのプライドを持たない人たちが、この舞台を作っているのではないか?」
……という危惧を通り越し、
「この崩れた絵を平気で人目にさらすってことは、崩れていることに、気づいてないのではないか?」
だったのよ。
前述の通り、原作の絵だって人体骨格的に正しいわけじゃない。それのみを正として見た場合、十分「崩れた、下手な絵」に見える。
少女マンガを理解できない人から見たら、原作のオスカルもアントワネットも、「子どもの落書き」ぐらい下手くそなまちがった絵なのよ。ルールに従ってデフォルメされているのに、そのルールを先天的に理解できない人から見たら、「ふくわらい?」くらい崩れた絵なの。
そーゆー人からみたら、原作の絵も、この舞台上のグダグダに崩れた絵も、どっちもどっち、どうせ崩れた変な絵でしかないってこと。
常識ではあり得ないくらい、崩れた絵が恥ずかしげもなく舞台で使われているこの現実は。
この絵が「崩れている」ことに気づかない人たちが、この舞台を作っている、ということ。
それはすなわち、
『ベルサイユのばら』を根本的に基本的に先天的に、理解できない人たちが、この舞台を作ったのではないか。
という絶望感だった。
そしてそれは、真実だった。
作・演出をする植田紳爾という人物は、最初から最後までついに『ベルサイユのばら』を理解できないままの人だった。
そう。
オープニングで、「これをオスカルと言ったら、オスカルへの冒涜だろ」という崩れた絵を使って平気であるということに象徴されたように。
てなことがあったから。
あれから何年? 何十年?
印刷技術は進歩し、マンガの小さな絵を、人間が手で大きく描き写す必要がなくなった。
原版をデジタル処理することによって、いくらでも、どんな加工でもできる時代になった。
もう映画館だって、似てない巨大な似顔絵看板を飾る必要はなくなった。宣伝用ポスター写真を拡大して看板にすればよい時代になった。
タカラヅカも、「素敵な絵ね」と言って、ヴィットリオ@オサとアンリエッタ@ふーちゃんの畳数枚サイズの写真を飾ることができるよーになった。
印刷技術の進歩、万歳!
これでもう、『ベルばら』のプロローグですでに絶望することもなくなった。
そこにあるのは、原作のイラストをまんま拡大したものだ。見慣れた絵だ。
植爺作品のひどさに、いずれ絶望するにしたって、幕が開くなり絶望、ということだけは回避された。
そこまで強く思わなくても、崩れたひどい絵を見て観客が失笑することはなくなった。……もちろん、マンガ絵を使うという演出のダサさに失笑がもれることがあったとしてもだ。
時の流れを感じたよ。
たかが、プロローグのマンガ絵1枚にね。
そして、そうやって印刷技術が変わって時代が変わったのに、それでも変わらない植爺のセンスと存在。
それに、感心し、改めて失笑した。
とゆー前振りではじめましょう、星組『ベルばら』の話。
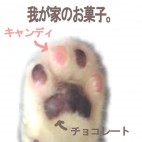
コメント