わたしのドレス。@DAYTIME HUSTLER
2005年11月19日 タカラヅカ わたしは洋服屋さんで、ドレスをオーダーメイドすることにしました。
自分で絵を描いて、「こんなふうにして欲しいの」と言いました。
いっぱい要望を聞いてもらって、素材にも凝ってしまいました。予算オーバーです。
先にドレスを受け取って、料金は分割で払うことにしました。
わたしは今とってもびんぼーなので、支払いはちょっと遅れがちです。ごめんなさい、もう少し待って。でも、絶対払いますから。
支払いが遅れがちなんだから、「早く払え!」と叱られるのは仕方ありません。わたしが「ごめんなさい」と謝りまくるのも仕方ありません。
でも変なんです。
お店の人は、
「あんたのデザインしたドレスは一般ウケしないよ。こんな田舎町じゃなく、もっと大きな町で作ればよかったんじゃないか? 洋服屋は慈善事業じゃないんだからな」
と言うんです。
えーと? わたしが着るために、わたしが注文したドレスです。なんで一般ウケが必要なの? 支払いが遅れがちなのは悪いけど、それとはチガウ話だよね?
洋服屋さんは、お客であるわたしのために、わたしの望んだドレスを売ってくれたら、そこでお仕事は終わりよね? 洋服屋さんがドレスを作り、わたしが支払いを済ませればいいだけの話よね?
わたしのデザインしたドレスを、他の人が「素敵ね。同じものを私も欲しいわ」と言わないからって、洋服屋さんがわたしを責めるのはお門違いよね?
わたしは洋服屋さん専属のデザイナーじゃありません。ただのお客です。どうして、デザインのことで文句を言われるの? 繰り返すけど、遅れている支払いのことで責められるのはわかるのよ。でも、「売れないデザインのドレスだ」と言われるのは理解できない。そんなの、わたしの自由でしょう。わたしがいいと思って、わたしのお金で作ったんだから!
と、こんな話ではじまりますが、『DAYTIME HUSTLER』の話。
ローリーが自費出版した本の売れ行きが悪いことで、出版社の人に責められていることに首を傾げつつ。
えーと、ローリーは彼自身のお金で本を作ったんだよね? つまり、出版社にとって彼は「お客」よね? ローリーが自分の金で作った本なんだから、売れようが売れまいが出版社は関係ないよね?
なんで出版社の人が、ローリーの本を持って書店に営業して回ってるんだろう。本はローリーのもので、出版社のものじゃないのに。
本が売れないと、印刷費を払えないとローリーが言ったから? それで仕方なく出版社の人が営業して回ってるの?
えーと、そんな契約自体おかしいって。自費出版本なんか、売れるわけないんだから。
売れる本なら、出版社が出してるよ。作者に原稿料や印税を払って。
ローリーに自費出版をさせた、ということは、この本を、金を出して買う人間はいないという出版社の判断よね? 作者以外には価値のない本だから、作者が金を出すのよね?
自費出版である以上、出版社の人間はその本の流通には関わらない。作者から出版料をもらっているのだから、そこで商売成立だ。本が売れようと売れまいとなにも損はしない。
もちろん、自費出版会社の中には、流通にも表面上責任を持つものもある。
「当社で出版すれば、書店にアナタの本が並びますよ!」と謳っている場合だ。
何故そんなことをするか。「お客」に「当社」で「出版」してほしいからだ。他の出版社でなく、自分のところで「自費」出版してほしいから。
「お客」というのは「本の作者」だ。お金を出すのは作者。「書店に本が並ぶ」というのは、作者へのセールスポイントだ。「当店でDVDレコーダを買うと、お好きな映画ソフトを1枚サービスしますよ」と同じ。
つまり、「書店に置いてもらう」のを前提にしている自費出版社なら、それをするのは当然のことだ。その本が、書店で売れる売れないは関係ない。「置いてもらう」のが、自費出版時の契約だからだ。
もしも書店に拒絶されたとしたら、それは出版社のミスだ。本の出来も作者の力量も関係ない。ローリーが責める側だよ、出版社の無能ぶりを。
だからわからないの。
出版社の人が、ローリーの本を営業して回っていることが。
いや、そこまではわからんでもないが、書店に置いてもらえないことでローリーを責めるのかが。謝るならわかるけど。
支払いが遅れているようだから、そのことでローリーが責められるのはぜんぜんかまわないんだけどね。
「書店に置いてもらえない」のは、関係ないじゃん。書店に置いてもらえるよーな本(つまり、ふつーに売れる本)なら、作者が金を出して自費出版しないって。売れない、書店にさえ拒否される本だから、わざわざ自分が金出して作ったんだっつーの。
なんかね、基本がまちがってるの。
「自費出版」の。
「田舎町の書店では、置いてもらえない」→「都会なら認められるかもしれないのに」→「ほんとうはすばらしい作品。こんなところには、理解できる人がいないだけ」
という意味で使ったんだろうけど。
それで、ラストの「都会へ出て詩人としてやり直す」につながるんだろうけど。
それなら、「自費出版」と「出版社」の認識がまちがってる。
「自費出版」には「出版社の人」なんて関係ない。出版社の人が出てくるなら、「印刷費早く払え」と督促するだけでなければおかしい。
「こんな田舎で詩集なんか売れない」と文句を言う出版社の人が出てくるなら、自費出版ではおかしい。出版社がローリーに印税を払って出版したことにしないと。
それにしたって、「会社」が決めた事業(詩集の出版)なんだから、作者に文句言うのはおかしいけどな。その事業を進めた会社内部の人に言うべきことだ。だからこの場合はローリーが出版社の人を騙して出版させたことにするしかないな。
わたしが気になったのは、ローレンスというキャラクタと、実際にかしげが演じている姿とに、どーも乖離感があったことなんだよね。
設定と現実が噛み合っていないというか。
以前に語った、「不良」という設定。
わたしにはローリーが不良には見えなかったし、女遊びし尽くしてきた男にも見えなかった。
次に「詩人」という設定。
専業プロ詩人、というものがイメージできずにいるわたしには、生活を顧みずに言葉の上でだけ美しいことを並べられても「現実を見られない人」と思えてしまう。
そしてさらに、今回長々と語った、「自費出版」。
現実にはありえない設定の出版社と客の関係。
冒頭の「自分のデザインで自分のお金でドレスを作った」だけなのに、「こんなデザインじゃ他の人は認めないよ!」と言われて、「すみません」と謝るのは変だ。
ローリー、騙されてる?
その出版社、変だよ。そして、そんな変なことをされて変だと思っていないローリーはやはり、ぬけてる? と思える。
そう。
かっこよくないんだ、ローリー。
いちいち、まぬけなんだ、あちこち。
でもなんか、設定上では「いい男」になっているらしいのが、気になる。
目に映っている姿はかっこわるいのに。
とまどうわたし。
自分で絵を描いて、「こんなふうにして欲しいの」と言いました。
いっぱい要望を聞いてもらって、素材にも凝ってしまいました。予算オーバーです。
先にドレスを受け取って、料金は分割で払うことにしました。
わたしは今とってもびんぼーなので、支払いはちょっと遅れがちです。ごめんなさい、もう少し待って。でも、絶対払いますから。
支払いが遅れがちなんだから、「早く払え!」と叱られるのは仕方ありません。わたしが「ごめんなさい」と謝りまくるのも仕方ありません。
でも変なんです。
お店の人は、
「あんたのデザインしたドレスは一般ウケしないよ。こんな田舎町じゃなく、もっと大きな町で作ればよかったんじゃないか? 洋服屋は慈善事業じゃないんだからな」
と言うんです。
えーと? わたしが着るために、わたしが注文したドレスです。なんで一般ウケが必要なの? 支払いが遅れがちなのは悪いけど、それとはチガウ話だよね?
洋服屋さんは、お客であるわたしのために、わたしの望んだドレスを売ってくれたら、そこでお仕事は終わりよね? 洋服屋さんがドレスを作り、わたしが支払いを済ませればいいだけの話よね?
わたしのデザインしたドレスを、他の人が「素敵ね。同じものを私も欲しいわ」と言わないからって、洋服屋さんがわたしを責めるのはお門違いよね?
わたしは洋服屋さん専属のデザイナーじゃありません。ただのお客です。どうして、デザインのことで文句を言われるの? 繰り返すけど、遅れている支払いのことで責められるのはわかるのよ。でも、「売れないデザインのドレスだ」と言われるのは理解できない。そんなの、わたしの自由でしょう。わたしがいいと思って、わたしのお金で作ったんだから!
と、こんな話ではじまりますが、『DAYTIME HUSTLER』の話。
ローリーが自費出版した本の売れ行きが悪いことで、出版社の人に責められていることに首を傾げつつ。
えーと、ローリーは彼自身のお金で本を作ったんだよね? つまり、出版社にとって彼は「お客」よね? ローリーが自分の金で作った本なんだから、売れようが売れまいが出版社は関係ないよね?
なんで出版社の人が、ローリーの本を持って書店に営業して回ってるんだろう。本はローリーのもので、出版社のものじゃないのに。
本が売れないと、印刷費を払えないとローリーが言ったから? それで仕方なく出版社の人が営業して回ってるの?
えーと、そんな契約自体おかしいって。自費出版本なんか、売れるわけないんだから。
売れる本なら、出版社が出してるよ。作者に原稿料や印税を払って。
ローリーに自費出版をさせた、ということは、この本を、金を出して買う人間はいないという出版社の判断よね? 作者以外には価値のない本だから、作者が金を出すのよね?
自費出版である以上、出版社の人間はその本の流通には関わらない。作者から出版料をもらっているのだから、そこで商売成立だ。本が売れようと売れまいとなにも損はしない。
もちろん、自費出版会社の中には、流通にも表面上責任を持つものもある。
「当社で出版すれば、書店にアナタの本が並びますよ!」と謳っている場合だ。
何故そんなことをするか。「お客」に「当社」で「出版」してほしいからだ。他の出版社でなく、自分のところで「自費」出版してほしいから。
「お客」というのは「本の作者」だ。お金を出すのは作者。「書店に本が並ぶ」というのは、作者へのセールスポイントだ。「当店でDVDレコーダを買うと、お好きな映画ソフトを1枚サービスしますよ」と同じ。
つまり、「書店に置いてもらう」のを前提にしている自費出版社なら、それをするのは当然のことだ。その本が、書店で売れる売れないは関係ない。「置いてもらう」のが、自費出版時の契約だからだ。
もしも書店に拒絶されたとしたら、それは出版社のミスだ。本の出来も作者の力量も関係ない。ローリーが責める側だよ、出版社の無能ぶりを。
だからわからないの。
出版社の人が、ローリーの本を営業して回っていることが。
いや、そこまではわからんでもないが、書店に置いてもらえないことでローリーを責めるのかが。謝るならわかるけど。
支払いが遅れているようだから、そのことでローリーが責められるのはぜんぜんかまわないんだけどね。
「書店に置いてもらえない」のは、関係ないじゃん。書店に置いてもらえるよーな本(つまり、ふつーに売れる本)なら、作者が金を出して自費出版しないって。売れない、書店にさえ拒否される本だから、わざわざ自分が金出して作ったんだっつーの。
なんかね、基本がまちがってるの。
「自費出版」の。
「田舎町の書店では、置いてもらえない」→「都会なら認められるかもしれないのに」→「ほんとうはすばらしい作品。こんなところには、理解できる人がいないだけ」
という意味で使ったんだろうけど。
それで、ラストの「都会へ出て詩人としてやり直す」につながるんだろうけど。
それなら、「自費出版」と「出版社」の認識がまちがってる。
「自費出版」には「出版社の人」なんて関係ない。出版社の人が出てくるなら、「印刷費早く払え」と督促するだけでなければおかしい。
「こんな田舎で詩集なんか売れない」と文句を言う出版社の人が出てくるなら、自費出版ではおかしい。出版社がローリーに印税を払って出版したことにしないと。
それにしたって、「会社」が決めた事業(詩集の出版)なんだから、作者に文句言うのはおかしいけどな。その事業を進めた会社内部の人に言うべきことだ。だからこの場合はローリーが出版社の人を騙して出版させたことにするしかないな。
わたしが気になったのは、ローレンスというキャラクタと、実際にかしげが演じている姿とに、どーも乖離感があったことなんだよね。
設定と現実が噛み合っていないというか。
以前に語った、「不良」という設定。
わたしにはローリーが不良には見えなかったし、女遊びし尽くしてきた男にも見えなかった。
次に「詩人」という設定。
専業プロ詩人、というものがイメージできずにいるわたしには、生活を顧みずに言葉の上でだけ美しいことを並べられても「現実を見られない人」と思えてしまう。
そしてさらに、今回長々と語った、「自費出版」。
現実にはありえない設定の出版社と客の関係。
冒頭の「自分のデザインで自分のお金でドレスを作った」だけなのに、「こんなデザインじゃ他の人は認めないよ!」と言われて、「すみません」と謝るのは変だ。
ローリー、騙されてる?
その出版社、変だよ。そして、そんな変なことをされて変だと思っていないローリーはやはり、ぬけてる? と思える。
そう。
かっこよくないんだ、ローリー。
いちいち、まぬけなんだ、あちこち。
でもなんか、設定上では「いい男」になっているらしいのが、気になる。
目に映っている姿はかっこわるいのに。
とまどうわたし。
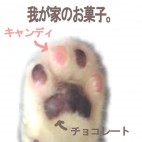
コメント