この感覚のズレはなんなんだろう?@長崎しぐれ坂
2005年5月15日 タカラヅカ「この芝居、誰がよろこぶんだろう……」
と、芝居が終わった段階で、わたしとkineさんは首をひねっていた。
わたしは「物語のルール」に則った話が好きなので、このあちこちセンスがめちゃくちゃな芝居にはとまどいしかなかったし、最後には笑えて笑えて仕方なくなってたんだけど。
主題歌をはじめとする、音楽のものすごさにも、笑いを通り越した感動があったしな。
もともとヅカの曲は時代錯誤にダサいものが多いんだけど、この『長崎しぐれ坂』の主題歌は素晴らしかった。
あー、なんだろこのメロディ……なんか聴いたことある……はっ、そうだ。うちのとーちゃん(70代)が毎日よろこんで聴いてる、昭和歌謡曲ってやつだ!!
昭和初期から中期、30年代とかに流行った音楽。このわたしですら生まれてねぇよ、な音楽。
「この芝居って、杉良太郎とか松平健とかが、他の劇場でやってそうな芝居ですよね」
と、kineさん。なんか具体的に、関東圏の劇場名をあげていたよーな?
そーなんだよなー。本物の男が演じてサマになるネタだよなー。そして、トド様もワタさんも、忠実に「男」を演じてるんだよなー。
わたしたちは「男」ではなく、「男役」を観にきてるんだけどな。
いろいろ話して、冒頭の疑問に対して出た結論。
植田(70代の男)が、自分の観たい芝居を作ったんだ。
だから、センスとか世界観とか、ものすげーズレてんだ……。
まあ、タカラヅカは年配の方もたくさん観に来られるんで、それはそれでいいのかもしれない。
少子化、趣味・価値観の多様化、不景気。
つまり、若者の数は少ない、タカラヅカでなくてもたのしいものは世の中いくらでもある、それに生の舞台は高すぎて、たくさんチケットを買えない。
そんな若者なんか見限って、金と時間をもてあましている中高年層にターゲットを絞るのも、ひとつの戦略かもしれない。
だからこの21世紀に『長崎しぐれ坂』で『ベルサイユのばら』なんだろう。時代錯誤もなんのその。
わたしも十分中年だし、時代劇は大好き、単純な筋立てのクサい話は大好きなんだが。
やっぱり植田芝居は「まちがっている」としか言いようがないわ……。
植爺の作品で、いつも疑問に思うことがある。
なんでこの人は、いつもわざわざ、いちばん無神経な言葉を選んで使うんだろう?
結果としてひどい行動でも、言葉で飾ることはできるんだよ。
「このままでは娘の命が危ないから、守るためにあえて、娘を出家させることにした」
というエピソードがあったとする。
娘の意思を無視して有無を言わさず出家をさせてしまうのはむごいことだけど、我が子の命を守るため、それも親の愛情。
行動はひどいけど、「仕方ないな」と思わせる原理だよね。
なのにそれをわざわざ、
「娘の意思なんて必要ない。親がその人生を決めることこそが正義」
という表現の仕方をするのよ。何故?
わざと悪ぶってるわけじゃないの。とってもナチュラルに、まちがった感覚で話が進むの。
……これは『長崎しぐれ坂』のエピソードじゃないけどさ。
これと同じよーな「感覚のズレ」があちこちにある。
たとえば伊佐次は「男の中の男」。男たちが惚れ込み、女が恋い焦がれる男だ。
しかしこの男、言動が、変。
それまでどんな男だったのか知らないが、初恋の相手おしまと再会してからは、確実に最低男になり下がっている。
かわいがっていたはずの弟分らしゃが死んだすぐあとに歌うのは、おしま(と、卯之助)のことを歌った、主題歌。でもこの歌、よーするに自分のことをいちばん大切にしてるよーな歌なんだよなあ……過去を懐かしむ歌、つーのはつまり、「そのころの自分」をなつかしがってるわけで……自己憐憫陶酔ソング……弟分が死んだすぐあとで。
そして、恋人・らしゃの死を嘆く少女芳蓮のことを、飲んだくれて怒鳴りつける。
これはひどい行動だよね。
でも、「らしゃのことを思って荒れているんだな」と、ちゃんと他のキャラによって説明が入るんだ。ほお、それなら荒れていてもわかるよ。自分が黙って耐えている横でびーびー泣く芳蓮に、つい怒鳴ってしまう気持ちもわかるよ。
なのに、わざわざ台詞でこれを打ち消すんだよな。
おしまのことを思って、荒れてるらしーのだわ……。
なんで? 伊佐次は「男の中の男」なんでしょう? なんで弟分が無惨な死に方をしても、ぜんぜん気にしないで女のことばっか考えてんの?
てか、らしゃのために荒れている、でいいじゃない。それで芳蓮にひどい態度を取った、でいいじゃん。
なんでわざわざ、最低な方に持っていくの?
伊佐次に愛想を尽かし、さそりが唐人屋敷を飛び出していく。外に出れば、さそりの命はない。
伊佐次もまた、外へ出ようとする。さそりのことが心配だから、と。
これならわかる。手下を心配して、命を危険にさらすのは「男の中の男」の行動だ。
なのに、わざわざ台詞でこれを打ち消すんだよな。
さそりを心配しているのはただの口実、ほんとはおしまのことを思って、外へ行こうとしているのだわ……。
なんで? 伊佐次は「男の中の男」なんでしょう? 今現在、手下の命が危険だっちゅーに、それを「口実」にできるわけ?
やっていることが、めちゃくちゃなのよ。
伊佐次のどこが、「男の中の男」なのかわからない。
ただの色ボケ自己中男やん……。
ここまで自分と、自分の女のことしか考えられない男を描きながら、「男の友情もの」としてラストを迎えるから、わたしはとまどったのよ。
おしまのことしかのーみそにないんだから、クライマックスでは当然おしまが出てくると思ったのよ。
わたしは原作を知らないが、ストーリーとキャラの表面的な行動は原作通りなんじゃないかと思う。とりあえず骨組みは出来ているようだから。
でもあちこち、変なの。
まるで、日本語で描かれたマンガを、日本語を読めない人が翻訳したみたいに。
マンガだから、絵だけでもストーリーはわかるじゃん。あ、ここで戦うんだ、ここで死ぬんだ、ここでラブシーンか。でも、台詞が読めないから、そのシーンが何故そういうことになっているのかは、わからない。
絵だけを見て、想像で台詞を埋めていく。
本当なら主人公は敵の事情を理解し、苦渋の選択で戦うことを選んだのに、戦っている絵だけを見て勝手に台詞をつけたから、主人公が嬉々として憎い敵と戦っていることになっている。
そんな「まちがい」を感じるのよ、植爺の作品には。
伊佐次の行動だけを写して、その心情は理解できていない。
だから、おかしな台詞を連発してしまう。
「男の友情」で、卯之助の腕の中で伊佐次が死んでもべつにかまわないのよ。
それまでを、「正しく」描いていれば。
そうじゃないから、この芝居はどこに行くんだと、わたしはうろたえたのよ……。
自分が観たいモノを描くのは勝手だが、やっぱどこか変だよ、植爺。
役者たちが力技で泣かせる芝居に昇華してるからって、作品のおかしさはどうしようもないから。
と、芝居が終わった段階で、わたしとkineさんは首をひねっていた。
わたしは「物語のルール」に則った話が好きなので、このあちこちセンスがめちゃくちゃな芝居にはとまどいしかなかったし、最後には笑えて笑えて仕方なくなってたんだけど。
主題歌をはじめとする、音楽のものすごさにも、笑いを通り越した感動があったしな。
もともとヅカの曲は時代錯誤にダサいものが多いんだけど、この『長崎しぐれ坂』の主題歌は素晴らしかった。
あー、なんだろこのメロディ……なんか聴いたことある……はっ、そうだ。うちのとーちゃん(70代)が毎日よろこんで聴いてる、昭和歌謡曲ってやつだ!!
昭和初期から中期、30年代とかに流行った音楽。このわたしですら生まれてねぇよ、な音楽。
「この芝居って、杉良太郎とか松平健とかが、他の劇場でやってそうな芝居ですよね」
と、kineさん。なんか具体的に、関東圏の劇場名をあげていたよーな?
そーなんだよなー。本物の男が演じてサマになるネタだよなー。そして、トド様もワタさんも、忠実に「男」を演じてるんだよなー。
わたしたちは「男」ではなく、「男役」を観にきてるんだけどな。
いろいろ話して、冒頭の疑問に対して出た結論。
植田(70代の男)が、自分の観たい芝居を作ったんだ。
だから、センスとか世界観とか、ものすげーズレてんだ……。
まあ、タカラヅカは年配の方もたくさん観に来られるんで、それはそれでいいのかもしれない。
少子化、趣味・価値観の多様化、不景気。
つまり、若者の数は少ない、タカラヅカでなくてもたのしいものは世の中いくらでもある、それに生の舞台は高すぎて、たくさんチケットを買えない。
そんな若者なんか見限って、金と時間をもてあましている中高年層にターゲットを絞るのも、ひとつの戦略かもしれない。
だからこの21世紀に『長崎しぐれ坂』で『ベルサイユのばら』なんだろう。時代錯誤もなんのその。
わたしも十分中年だし、時代劇は大好き、単純な筋立てのクサい話は大好きなんだが。
やっぱり植田芝居は「まちがっている」としか言いようがないわ……。
植爺の作品で、いつも疑問に思うことがある。
なんでこの人は、いつもわざわざ、いちばん無神経な言葉を選んで使うんだろう?
結果としてひどい行動でも、言葉で飾ることはできるんだよ。
「このままでは娘の命が危ないから、守るためにあえて、娘を出家させることにした」
というエピソードがあったとする。
娘の意思を無視して有無を言わさず出家をさせてしまうのはむごいことだけど、我が子の命を守るため、それも親の愛情。
行動はひどいけど、「仕方ないな」と思わせる原理だよね。
なのにそれをわざわざ、
「娘の意思なんて必要ない。親がその人生を決めることこそが正義」
という表現の仕方をするのよ。何故?
わざと悪ぶってるわけじゃないの。とってもナチュラルに、まちがった感覚で話が進むの。
……これは『長崎しぐれ坂』のエピソードじゃないけどさ。
これと同じよーな「感覚のズレ」があちこちにある。
たとえば伊佐次は「男の中の男」。男たちが惚れ込み、女が恋い焦がれる男だ。
しかしこの男、言動が、変。
それまでどんな男だったのか知らないが、初恋の相手おしまと再会してからは、確実に最低男になり下がっている。
かわいがっていたはずの弟分らしゃが死んだすぐあとに歌うのは、おしま(と、卯之助)のことを歌った、主題歌。でもこの歌、よーするに自分のことをいちばん大切にしてるよーな歌なんだよなあ……過去を懐かしむ歌、つーのはつまり、「そのころの自分」をなつかしがってるわけで……自己憐憫陶酔ソング……弟分が死んだすぐあとで。
そして、恋人・らしゃの死を嘆く少女芳蓮のことを、飲んだくれて怒鳴りつける。
これはひどい行動だよね。
でも、「らしゃのことを思って荒れているんだな」と、ちゃんと他のキャラによって説明が入るんだ。ほお、それなら荒れていてもわかるよ。自分が黙って耐えている横でびーびー泣く芳蓮に、つい怒鳴ってしまう気持ちもわかるよ。
なのに、わざわざ台詞でこれを打ち消すんだよな。
おしまのことを思って、荒れてるらしーのだわ……。
なんで? 伊佐次は「男の中の男」なんでしょう? なんで弟分が無惨な死に方をしても、ぜんぜん気にしないで女のことばっか考えてんの?
てか、らしゃのために荒れている、でいいじゃない。それで芳蓮にひどい態度を取った、でいいじゃん。
なんでわざわざ、最低な方に持っていくの?
伊佐次に愛想を尽かし、さそりが唐人屋敷を飛び出していく。外に出れば、さそりの命はない。
伊佐次もまた、外へ出ようとする。さそりのことが心配だから、と。
これならわかる。手下を心配して、命を危険にさらすのは「男の中の男」の行動だ。
なのに、わざわざ台詞でこれを打ち消すんだよな。
さそりを心配しているのはただの口実、ほんとはおしまのことを思って、外へ行こうとしているのだわ……。
なんで? 伊佐次は「男の中の男」なんでしょう? 今現在、手下の命が危険だっちゅーに、それを「口実」にできるわけ?
やっていることが、めちゃくちゃなのよ。
伊佐次のどこが、「男の中の男」なのかわからない。
ただの色ボケ自己中男やん……。
ここまで自分と、自分の女のことしか考えられない男を描きながら、「男の友情もの」としてラストを迎えるから、わたしはとまどったのよ。
おしまのことしかのーみそにないんだから、クライマックスでは当然おしまが出てくると思ったのよ。
わたしは原作を知らないが、ストーリーとキャラの表面的な行動は原作通りなんじゃないかと思う。とりあえず骨組みは出来ているようだから。
でもあちこち、変なの。
まるで、日本語で描かれたマンガを、日本語を読めない人が翻訳したみたいに。
マンガだから、絵だけでもストーリーはわかるじゃん。あ、ここで戦うんだ、ここで死ぬんだ、ここでラブシーンか。でも、台詞が読めないから、そのシーンが何故そういうことになっているのかは、わからない。
絵だけを見て、想像で台詞を埋めていく。
本当なら主人公は敵の事情を理解し、苦渋の選択で戦うことを選んだのに、戦っている絵だけを見て勝手に台詞をつけたから、主人公が嬉々として憎い敵と戦っていることになっている。
そんな「まちがい」を感じるのよ、植爺の作品には。
伊佐次の行動だけを写して、その心情は理解できていない。
だから、おかしな台詞を連発してしまう。
「男の友情」で、卯之助の腕の中で伊佐次が死んでもべつにかまわないのよ。
それまでを、「正しく」描いていれば。
そうじゃないから、この芝居はどこに行くんだと、わたしはうろたえたのよ……。
自分が観たいモノを描くのは勝手だが、やっぱどこか変だよ、植爺。
役者たちが力技で泣かせる芝居に昇華してるからって、作品のおかしさはどうしようもないから。
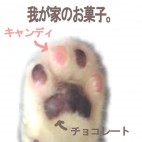
コメント