深い井戸の底から、目を上げて。@マラケシュ・紅の墓標
2005年3月26日 タカラヅカ その昔。
宝塚大劇場で、『螺旋のオルフェ』とゆー芝居が上演された。
演出家のファンだったのと、ダーリンが組替えになったっちゅーんで、わたしはいそいそと初日に観に行った。3列目の下手席だった。
あのときの空気を、忘れない(笑)。
幕が下りる。
しかし、客席はしんとしている。
幕が下りきった。
客席には、困惑したささやきがあがりはじめた。
客電がつき、アナウンスが流れる。
客席から、ぱらぱらと拍手が起こった。
芝居が終わったことに、客がだれも気づかないって、どうよ?(笑)
『螺旋』初日を観て、わたしは内心腹を抱えて笑っていた。やったな、オギー。見事なまでの失敗作。
『螺旋のオルフェ』は、「駄作」ではない。「失敗作」なんだ。
駄作と失敗作なら、失敗作の方がすばらしい、という例のような、華麗な失敗作。いろんな意味でおもしろかった。わたしは『螺旋』を好きだし、すばらしいと思っている。
が、この作品を絶賛しちゃいかんことも、わかっている。だってコレ、失敗作だし。てきとーな作家ならこの程度の失敗でもほめていいけど、オギーはもっといいものを創れる人だから、コレをほめる気にはなれない。失敗は失敗だ。
にしても、才能ある人の失敗作ってのは、ぼんくら作家のつまんねー及第作より、はるかに心を動かされ、また勉強になるのだなあ、と、そんなことも感心したさ。
そして時は流れ、昨日3月25日。『螺旋のオルフェ』以来数年ぶりの、荻田浩一・大劇場芝居作品初日。
「緑野さんはまた、失敗作だって吠えてるかと思いました(笑)」
と、チェリさん。
いやそんな、吠えないですよ。
だって、『螺旋のオルフェ』より、マシだもん(笑)。
幕が降りるときに、とまどいがちとはいえ拍手あったじゃん。『螺旋』初日を観た者からすりゃ、快挙だわ。
にしてもオギー……。
本気で、大劇場向け作家やないんやな。
わたしはエンタメ好きで、大衆向け劇場である宝塚大劇場でこそ実力を発揮できる作家をいちばん評価している。はばひろい年代のいろんな価値観を持つ人たちをたのしませる力。それでいて、マニアックな観客のハートもくすぐることのできる作品。それこそが、真のエンターテイメントだと思っている。
一部の「高尚な」人たちしかわからない、また興味も持たないよーな作品には、好意を持てない。わずかな人たちだけをよろこばせることなんか、たくさんの人をよろこばせるより簡単じゃん。たとえば、料理の下手な人でも、その人の子どもだけは「ママの料理がいちばんおいしい」って言うよーなもんでさ。誰だってわずかな特定対象だけなら、たのしませることはできるのよ。
だから、オギーの「大衆向けではない」持ち味は、なんとも微妙だ。
彼はわざとやっているのだろーか。それとも天然なんだろーか。
「観客に理解できるかどうか」というラインを、わかっていながら「わかる奴だけついてこい」と思ってぶっちぎっているのか、あるいは本当になにもわかっていないのか。
モノを書いていると、時折不安になる。
はたして、この文章は正しく機能しているだろうか。ストーリーは伝わっているだろうか。なにをやっているのか、なにを言っているのかわからない、なんてことにはなっていないだろうか。
……小説を書いたときなんかは、まずソレがいちばん気になる。で、他人に読んでもらって、評価をあおぐ。ねえねえ、意味わかる? 話、つながってるかなあ?
数学的な、組み立て。情緒的なこと以前の構成。それは「技術」のみで構築できる部分だ。テーマだとか萌えだとか、あるいは叫びたいメッセージ、高尚な想いなんかも、その基本的なものを正しく作り上げた上ではじめて必要になってくる。骨組みが正しくできていないのに、そこにどれだけ美しい化粧をしても、一歩動いたら全部ぐちゃぐちゃに崩壊しちゃうよ。
他人の目は、必要だ。仕事で書く文章など、自分では何十回と読み返すので、読んでいるうちになにがなんだかわからなくなる。自分は先の先まで何十回も読んでいるし知っているので、「はじめて読む人の目線」を失ってしまう。それがこわい。
もちろん、「**ちゃんになったつもりで読んでみよう」とか、具体的な友だちのことを考えて、その人の「架空の目線」を想像して読んだりして、自分で補っているつもりだが。
オギーの大劇場作品で気になるのは、この「他人の目線」。
他人なんかどーでもいー、やりたいことをやるだけだ。わかる人だけわかればいい。
そう思っているのか。
もちろん、大劇場作品であるという「譲歩」は見えるので、完全に自己陶酔世界に入っているのでないことは、わかるんだ。彼なりに、「タカラヅカらしい」「わかりやすい作品」を作ろうとしている。
ただ、その「譲歩」が、ひどく中途半端だ。
彼本来の精神世界からすれば、わかりやすい大衆向けのモノを創っている。でも、足りてない。一般大衆、しかも2500人も収容できる巨大劇場を相手にした作品じゃない。
それは、わざとなのか?
これだけ譲歩したんだから、あとは知らない。最低限の仕事はしたから、あとは好きにさせてもらう。クリエイターとしての矜持は譲れない。
そう思っているのか。
ほんとのとこなんか、知らない。
知らないけどな。
誰か、第三者が監修してやれよ。
と、心から思うんだ。
せっかく、すばらしいものを創ってるんだよ。美しく、高度なものを創っているの。
なのに、「他人の目」がないために、スベってるの。
阿呆で怠惰な一般大衆にこびるのなんかごめんだと思っているのかもしれないが、もったいないよ。オギーに最低限の「わかりやすさ」が加われば、天下無敵になるのに。
作品のレベルをあげるためだ。本人が嫌がっても、誰か監修者をつけろ。
「わかりやすくする」ことは、一概に作品レベルを下げることじゃないんだ。真に能力のある人なら、「わかりやすく」かつ「高尚なモノ」も創れるはずだよ。
もったいない……もったいないよぅ。
才能のある人が、大衆性を否定してコアでディープな小さな世界にハマっていくのを見るのは、かなしいのよ。世界は小さければ小さいほど、心地よいものだから。崇拝者と理解者だけで固めて、否定者のことは軽蔑して排除して、自分たちだけで「高尚なモノ」に酔う。
才能があるだけに、陥りやすい罠。
オギーがそんなふうになってしまわないことを、心から祈る。
いらん心配までしてしまうほど、今回の大劇場作品『マラケシュ・紅の墓標』は、オギーらしい、わかりにくい話だった(笑)。
ものすごい、うまいんだけどなあ。
粗はいろいろあるものの、あちこち「すげー」の連続だった。
なのにどーしてこう、一般大衆を置き去りにするのか。
わたしは夢中で観ていたので、周囲の反応はよくわからないんだが、チェリさん曰く、爆睡者続出だったらしいぞ、初日なのに。2階の隅で観ていたわたしとちがい、チェリさんは1階の真ん中あたりにいたのに。舞台へ集中しやすいところにいたはずなのに。なのに、みんな退屈して寝ちゃうんだ。
かなしいことだ。
宝塚大劇場で、『螺旋のオルフェ』とゆー芝居が上演された。
演出家のファンだったのと、ダーリンが組替えになったっちゅーんで、わたしはいそいそと初日に観に行った。3列目の下手席だった。
あのときの空気を、忘れない(笑)。
幕が下りる。
しかし、客席はしんとしている。
幕が下りきった。
客席には、困惑したささやきがあがりはじめた。
客電がつき、アナウンスが流れる。
客席から、ぱらぱらと拍手が起こった。
芝居が終わったことに、客がだれも気づかないって、どうよ?(笑)
『螺旋』初日を観て、わたしは内心腹を抱えて笑っていた。やったな、オギー。見事なまでの失敗作。
『螺旋のオルフェ』は、「駄作」ではない。「失敗作」なんだ。
駄作と失敗作なら、失敗作の方がすばらしい、という例のような、華麗な失敗作。いろんな意味でおもしろかった。わたしは『螺旋』を好きだし、すばらしいと思っている。
が、この作品を絶賛しちゃいかんことも、わかっている。だってコレ、失敗作だし。てきとーな作家ならこの程度の失敗でもほめていいけど、オギーはもっといいものを創れる人だから、コレをほめる気にはなれない。失敗は失敗だ。
にしても、才能ある人の失敗作ってのは、ぼんくら作家のつまんねー及第作より、はるかに心を動かされ、また勉強になるのだなあ、と、そんなことも感心したさ。
そして時は流れ、昨日3月25日。『螺旋のオルフェ』以来数年ぶりの、荻田浩一・大劇場芝居作品初日。
「緑野さんはまた、失敗作だって吠えてるかと思いました(笑)」
と、チェリさん。
いやそんな、吠えないですよ。
だって、『螺旋のオルフェ』より、マシだもん(笑)。
幕が降りるときに、とまどいがちとはいえ拍手あったじゃん。『螺旋』初日を観た者からすりゃ、快挙だわ。
にしてもオギー……。
本気で、大劇場向け作家やないんやな。
わたしはエンタメ好きで、大衆向け劇場である宝塚大劇場でこそ実力を発揮できる作家をいちばん評価している。はばひろい年代のいろんな価値観を持つ人たちをたのしませる力。それでいて、マニアックな観客のハートもくすぐることのできる作品。それこそが、真のエンターテイメントだと思っている。
一部の「高尚な」人たちしかわからない、また興味も持たないよーな作品には、好意を持てない。わずかな人たちだけをよろこばせることなんか、たくさんの人をよろこばせるより簡単じゃん。たとえば、料理の下手な人でも、その人の子どもだけは「ママの料理がいちばんおいしい」って言うよーなもんでさ。誰だってわずかな特定対象だけなら、たのしませることはできるのよ。
だから、オギーの「大衆向けではない」持ち味は、なんとも微妙だ。
彼はわざとやっているのだろーか。それとも天然なんだろーか。
「観客に理解できるかどうか」というラインを、わかっていながら「わかる奴だけついてこい」と思ってぶっちぎっているのか、あるいは本当になにもわかっていないのか。
モノを書いていると、時折不安になる。
はたして、この文章は正しく機能しているだろうか。ストーリーは伝わっているだろうか。なにをやっているのか、なにを言っているのかわからない、なんてことにはなっていないだろうか。
……小説を書いたときなんかは、まずソレがいちばん気になる。で、他人に読んでもらって、評価をあおぐ。ねえねえ、意味わかる? 話、つながってるかなあ?
数学的な、組み立て。情緒的なこと以前の構成。それは「技術」のみで構築できる部分だ。テーマだとか萌えだとか、あるいは叫びたいメッセージ、高尚な想いなんかも、その基本的なものを正しく作り上げた上ではじめて必要になってくる。骨組みが正しくできていないのに、そこにどれだけ美しい化粧をしても、一歩動いたら全部ぐちゃぐちゃに崩壊しちゃうよ。
他人の目は、必要だ。仕事で書く文章など、自分では何十回と読み返すので、読んでいるうちになにがなんだかわからなくなる。自分は先の先まで何十回も読んでいるし知っているので、「はじめて読む人の目線」を失ってしまう。それがこわい。
もちろん、「**ちゃんになったつもりで読んでみよう」とか、具体的な友だちのことを考えて、その人の「架空の目線」を想像して読んだりして、自分で補っているつもりだが。
オギーの大劇場作品で気になるのは、この「他人の目線」。
他人なんかどーでもいー、やりたいことをやるだけだ。わかる人だけわかればいい。
そう思っているのか。
もちろん、大劇場作品であるという「譲歩」は見えるので、完全に自己陶酔世界に入っているのでないことは、わかるんだ。彼なりに、「タカラヅカらしい」「わかりやすい作品」を作ろうとしている。
ただ、その「譲歩」が、ひどく中途半端だ。
彼本来の精神世界からすれば、わかりやすい大衆向けのモノを創っている。でも、足りてない。一般大衆、しかも2500人も収容できる巨大劇場を相手にした作品じゃない。
それは、わざとなのか?
これだけ譲歩したんだから、あとは知らない。最低限の仕事はしたから、あとは好きにさせてもらう。クリエイターとしての矜持は譲れない。
そう思っているのか。
ほんとのとこなんか、知らない。
知らないけどな。
誰か、第三者が監修してやれよ。
と、心から思うんだ。
せっかく、すばらしいものを創ってるんだよ。美しく、高度なものを創っているの。
なのに、「他人の目」がないために、スベってるの。
阿呆で怠惰な一般大衆にこびるのなんかごめんだと思っているのかもしれないが、もったいないよ。オギーに最低限の「わかりやすさ」が加われば、天下無敵になるのに。
作品のレベルをあげるためだ。本人が嫌がっても、誰か監修者をつけろ。
「わかりやすくする」ことは、一概に作品レベルを下げることじゃないんだ。真に能力のある人なら、「わかりやすく」かつ「高尚なモノ」も創れるはずだよ。
もったいない……もったいないよぅ。
才能のある人が、大衆性を否定してコアでディープな小さな世界にハマっていくのを見るのは、かなしいのよ。世界は小さければ小さいほど、心地よいものだから。崇拝者と理解者だけで固めて、否定者のことは軽蔑して排除して、自分たちだけで「高尚なモノ」に酔う。
才能があるだけに、陥りやすい罠。
オギーがそんなふうになってしまわないことを、心から祈る。
いらん心配までしてしまうほど、今回の大劇場作品『マラケシュ・紅の墓標』は、オギーらしい、わかりにくい話だった(笑)。
ものすごい、うまいんだけどなあ。
粗はいろいろあるものの、あちこち「すげー」の連続だった。
なのにどーしてこう、一般大衆を置き去りにするのか。
わたしは夢中で観ていたので、周囲の反応はよくわからないんだが、チェリさん曰く、爆睡者続出だったらしいぞ、初日なのに。2階の隅で観ていたわたしとちがい、チェリさんは1階の真ん中あたりにいたのに。舞台へ集中しやすいところにいたはずなのに。なのに、みんな退屈して寝ちゃうんだ。
かなしいことだ。
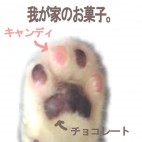
コメント