バラライカ、いつもお前を夢に見る。
2003年10月16日 その他 なんか、なつかしい歌をいろいろ検索してみました。
拒否権のない子どものころに、教師から命令されて歌っていた歌。
いちばんひどかったのが、中学時代。
わたしは中学のとき、音楽教育を受けさせてもらえなかった。
わたしだけでなく、わたしの学年全部。
もちろん科目に「音楽」はあった。
あったけど、あれは授業じゃなかった。
3年間ずーっと、音楽教師の子どもの話を聞かされてたんだよね(教師は持ち上がりだったから、3年間同じ人)。
楽器も習わなかったし、楽譜の読み方も習わなかったし、レコード鑑賞もなかった。音楽史も作曲家の名前も知らない。
ただひたすら、来る日も来る日も、せんせーの赤ちゃんの話を聞いていた。
おかげで、高校に入ってから苦労したよ。
中学生のときに習っていて当然のことを、なにも知らなかったから。
中学で購入しているはずの楽器も、クラスでわたしひとりだけ持ってなかったし、触ったこともなかった。
高校の音楽の先生に、「あなた中学3年間なにやってたの?」と真顔で質問されて、こまったよ。
同じ中学出身の他の高校に行った友だちに愚痴ったら、
「音楽を選択するからいけないのよ。うちの中学出身の人は、音楽を選択しないものよ」
と言われてさらにびっくりさ。
そっか、うちの中学出身者は、高校の選択科目の枠が他の中学の人より少ないのか……当然だよな、教育受けてないもんな。
ってしかし、うちの高校、音楽は選択じゃなくて必須科目だったんだよ。泣。
中学時代の音楽の授業では、教科書を開くこともなかった。
だから教科書に載っている歌はまったく知らない。
中学3年間の音楽の授業でひたすら歌った歌は、
『バラライカ』
だった。
おかげで、時折ものすごーくこの歌が聴きたくなる。歌いたくなる(笑)。
ビバ、インターネット。
ブラボー、インターネット。
聞くことができたわ、『バラライカ』。ああ、なつかしい。
暗い暗い曲調で、生きる苦しみを歌う歌。
4番まであるけど、3番まではただただ苦しみ。ひたすら苦しみ。とにかく苦しみ。
呪うような感じで、「バラライカ」と繰り返す。
4番でようやく、苦しみを乗り越えて生きよう、と歌う。しかし曲調は暗い呪い歌のまま。
「苦しい仕事に疲れ果てて 帰って寝るだけ」だとか「着た切りすずめの貧乏暮らし 優しい言葉に いつも飢えている」とか、そんな歌だよ?
これ、中学生に歌わせる意味があるのか?
3年間、毎時間2回以上歌わされたんだけど?
授業開始に1回、終わりに1回。声が小さいと、やりなおし。
歌わされていない間はずーっと、せんせーの赤ちゃんが立ったの坐ったの喋ったのって話。
今も、ノブヨ先生の呪うよーな暗い歌声が耳に残っているよ……。
バラライカ、バラライカ……。
あと忘れられないのが、『ポーリシュカ・ポーレ』。
教科書に載っている『ポーリシュカ・ポーレ』は日本人が勝手に詩をつけただけの嘘の歌で、ほんとうの歌詞はチガウんだ、と言って、プリントが配られた。
貧しい民衆が立ち上がって戦う歌だと教えられ、みんなで歌いました……。
たしか教育実習生が指揮を執っていたと思うけど、その後ろでうなずいていたのが、ノブヨ先生。
たしかに、教科書に載っていた美しい言葉ばかりの歌詞とはまったくちがい、血なまぐさい戦いを連想させる勇ましい歌だったよ。
少し前に、アイドルドラマで『ポーリシュカ・ポーレ』が使われていることがあった。友人が「なんでロシア民謡が主題歌なのかしら」と言っていたので、「さあ? 戦いの歌だからじゃないの?」と答えておいたんだが、この認識は世界的に正しいのだろうか?
なんにせよ、強烈に印象に残っている想い出の1曲であることには、ちがいない。
ビバ、インターネット。
ブラボー、インターネット。
聞くことができたわ、『ポーリシュカ・ポーレ』。ああ、なつかしい。
生きる苦しみの歌を毎時間歌い、戦う民衆の歌を熱唱する中学生たち。
……あー……なんであんなに偏った歌しか歌わせてもらえなかったんだ……。
でもやっぱり、歌いたいなあ、『バラライカ』。
カラオケに入ってないかなあ。
世の中を呪うよーな暗い声で歌うのよー。もの悲しくされど力強く大きな声で歌うのよー。
ストレス解消にいいかもしれない(笑)。
拒否権のない子どものころに、教師から命令されて歌っていた歌。
いちばんひどかったのが、中学時代。
わたしは中学のとき、音楽教育を受けさせてもらえなかった。
わたしだけでなく、わたしの学年全部。
もちろん科目に「音楽」はあった。
あったけど、あれは授業じゃなかった。
3年間ずーっと、音楽教師の子どもの話を聞かされてたんだよね(教師は持ち上がりだったから、3年間同じ人)。
楽器も習わなかったし、楽譜の読み方も習わなかったし、レコード鑑賞もなかった。音楽史も作曲家の名前も知らない。
ただひたすら、来る日も来る日も、せんせーの赤ちゃんの話を聞いていた。
おかげで、高校に入ってから苦労したよ。
中学生のときに習っていて当然のことを、なにも知らなかったから。
中学で購入しているはずの楽器も、クラスでわたしひとりだけ持ってなかったし、触ったこともなかった。
高校の音楽の先生に、「あなた中学3年間なにやってたの?」と真顔で質問されて、こまったよ。
同じ中学出身の他の高校に行った友だちに愚痴ったら、
「音楽を選択するからいけないのよ。うちの中学出身の人は、音楽を選択しないものよ」
と言われてさらにびっくりさ。
そっか、うちの中学出身者は、高校の選択科目の枠が他の中学の人より少ないのか……当然だよな、教育受けてないもんな。
ってしかし、うちの高校、音楽は選択じゃなくて必須科目だったんだよ。泣。
中学時代の音楽の授業では、教科書を開くこともなかった。
だから教科書に載っている歌はまったく知らない。
中学3年間の音楽の授業でひたすら歌った歌は、
『バラライカ』
だった。
おかげで、時折ものすごーくこの歌が聴きたくなる。歌いたくなる(笑)。
ビバ、インターネット。
ブラボー、インターネット。
聞くことができたわ、『バラライカ』。ああ、なつかしい。
暗い暗い曲調で、生きる苦しみを歌う歌。
4番まであるけど、3番まではただただ苦しみ。ひたすら苦しみ。とにかく苦しみ。
呪うような感じで、「バラライカ」と繰り返す。
4番でようやく、苦しみを乗り越えて生きよう、と歌う。しかし曲調は暗い呪い歌のまま。
「苦しい仕事に疲れ果てて 帰って寝るだけ」だとか「着た切りすずめの貧乏暮らし 優しい言葉に いつも飢えている」とか、そんな歌だよ?
これ、中学生に歌わせる意味があるのか?
3年間、毎時間2回以上歌わされたんだけど?
授業開始に1回、終わりに1回。声が小さいと、やりなおし。
歌わされていない間はずーっと、せんせーの赤ちゃんが立ったの坐ったの喋ったのって話。
今も、ノブヨ先生の呪うよーな暗い歌声が耳に残っているよ……。
バラライカ、バラライカ……。
あと忘れられないのが、『ポーリシュカ・ポーレ』。
教科書に載っている『ポーリシュカ・ポーレ』は日本人が勝手に詩をつけただけの嘘の歌で、ほんとうの歌詞はチガウんだ、と言って、プリントが配られた。
貧しい民衆が立ち上がって戦う歌だと教えられ、みんなで歌いました……。
たしか教育実習生が指揮を執っていたと思うけど、その後ろでうなずいていたのが、ノブヨ先生。
たしかに、教科書に載っていた美しい言葉ばかりの歌詞とはまったくちがい、血なまぐさい戦いを連想させる勇ましい歌だったよ。
少し前に、アイドルドラマで『ポーリシュカ・ポーレ』が使われていることがあった。友人が「なんでロシア民謡が主題歌なのかしら」と言っていたので、「さあ? 戦いの歌だからじゃないの?」と答えておいたんだが、この認識は世界的に正しいのだろうか?
なんにせよ、強烈に印象に残っている想い出の1曲であることには、ちがいない。
ビバ、インターネット。
ブラボー、インターネット。
聞くことができたわ、『ポーリシュカ・ポーレ』。ああ、なつかしい。
生きる苦しみの歌を毎時間歌い、戦う民衆の歌を熱唱する中学生たち。
……あー……なんであんなに偏った歌しか歌わせてもらえなかったんだ……。
でもやっぱり、歌いたいなあ、『バラライカ』。
カラオケに入ってないかなあ。
世の中を呪うよーな暗い声で歌うのよー。もの悲しくされど力強く大きな声で歌うのよー。
ストレス解消にいいかもしれない(笑)。
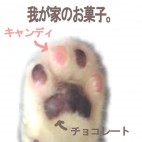
コメント