手段のための目的。@恒例夏の家族行動
2003年8月11日 家族 鉄道オタクの父がまた、「電車に乗りたい」と言い出した。
「京阪の2階建て特急に乗って、比叡山に行こう」
あの……京阪特急って、思い切り通勤特急ですが? ふつーの勤め人が通勤のために乗っている電車ですが?
それに、なんでわざわざ比叡山なの?
「比叡山に行けば、ロープウェイとケーブルカーに乗れるんだぞ」
乗れる、って……目的はソレかい。
父の旅行はいつもこうだ。
目的地は後付け。先に「なにに乗りたいから」という発想で決められる。
乗り物が先。乗り物にさえ乗ることができたら、どこにも行かずに帰ってきてもいいくらいらしい。
予定段階でモメにモメて(なんでこー、父も母もわがままで気まぐれなんだ?!)、行くのが相当嫌になったりもしたが、とりあえず比叡山に向けて日帰り旅行出発。
比叡山に行くのは何度目だろう。寺社仏閣好きの家庭に育ったために、近畿地方の主な寺には大抵行ってるからな。記憶が混ざってしまって、どこがどこやら。
しかし、こういう大きなお寺と、テーマパークと化した空間は素晴らしいね。外国の教会とかもそうだけど、信仰の場というのはとても美しい独特の宇宙がある。
根本中堂の、厨子の中で見ることはできないご本尊と、その前を照らす1200年間途絶えたことがないという不滅の法灯、そしてそれらとわたしたちを隔てる深淵。
美しいものはどこか、こわさを秘めている。
……娯楽のない時代に、この空間を作ったわけだから、すげえよな。ディズニーランドもUSJもないわけだからな。ふつーの人が苦労して山のてっぺんまで登ってきて、そこにこの空間が広がっていたら、そりゃびっくりするさ。こんな世界があったなんて!と感動するさ。はじめてのヴァーチャル・リアリティ。ひとの手によって構築された別世界を見るという経験。神も仏も、信じたくなるだろうさ。
とくに信仰を持っていないわたしでも、ははぁっ!とひれ伏したくなる空間だからな。
愉快だったのは横川の角大師だ。
わたしたち家族も、横川にまではそれまで行ったことがなかったんだ。はじめて横川に行って、清水寺に似た作りと、似てもにつかないカラーリングの横川中堂に驚嘆した、そのあと。
おみくじの元祖だとかいう元三大師堂に行ったのね。
そこにはあちこちに、とても愉快なお札が貼ってあった。
ひとめで「悪魔」だと思える姿形。
お寺に、悪魔?
それは角大師という疫神らしい。角大師の姿を写したお札を入り口に貼れば疫病封じになるし、また身につければ魔よけになるらしい。
「じつにいい味をだしている」
と、弟。デジカメにその姿をおさめながら、しみじみと言う。
ほんとに素晴らしい造形だ。角大師。ここでしかグッズが手に入らないのがまたレアだわ。わたしは角大師様の根付けを買った。だってわたし、今年厄年なんだよ。
「なんつーか、ゲームキャラみたい」
「それを見た人に『モトネタなに?』って聞かれそうだよな」
「『メガテン』とかに出てそう」
あやしくていい感じだ、角大師様。かなりお気に入り。今度また、時間のあるときにゆっくりと来よう。4時閉堂ってことで、ここにたどりついたときにはもう時間切れ、ろくに見ることができなかったのよねえ。
帰りは琵琶湖花火大会へ。
淀川花火大会がホームグラウンドなわたしたち、琵琶湖のことはなにもわかっていません。ビューポイントがどこなのか、どうすればいいのかさっぱりわからないままに、行きがけの駄賃程度の気持ちで参加。
琵琶湖花火大会は、淀川花火大会の半分の規模。だけど人出は同じ40万人。……これだけは前もって情報誌で押さえてあった。
半分の規模なのに、人出は同じ、ってなによそれ。さいてーじゃん。
淀川のものすげえ混雑ぶりを知っているだけに、辟易してたんだけど。
やっぱ田舎はいいよなっ。
大阪とは都市の作りがまったくチガウのだ。
なんなの、この道路のだだっ広さは。
淀川とちがって開放感あふれている。しかも。
その大きな道路が、完全に交通規制され歩行者天国になっているのだ。
最寄り駅から湖岸まで、歩行者天国だよ?
かなりな距離だよ?
相当な広さだよ?
「祭りとは本来、都市機能をストップさせて行うものなんだ」
と、史学科卒の弟が感慨深くつぶやく。
これだけの距離、これだけの道路をたかが「祭り」のために機能停止させるなんて。大阪ではありえない。そんなことをしたら経済に支障を来す。パニックになる。
だけど田舎では、それが可能なんだ。すごい。
都市をあげての「祭り」だ、淀川と同じ40万人が参加しているはずなのに、人混みの密度は比べモノにならない。ガラガラ。ストレス最小。湖岸へとまっすぐ伸びた大きな道路は、どこからでもよく見える。なんて楽なの、この花火見物。
打ち上げの規模は半分だとしても、演出のちがいで遜色ないモノになっていた。
淀川の花火は、縦に重ねて上がる。
琵琶湖の花火は、横に連なって上がる。
淀川では、打ち上げられる花火のあまりの数に、空が煙で白んでしまう。重ねて重ねて、同じところに打ち上げられるからだ。
琵琶湖の花火は、空間の広さを最大限に利用し、夜空全体に広がる。ひとつずつが重なることはないから、奥行きはない。
どちらがすばらしいと決めるものではないだろう。
まったくチガウふたつの花火大会を見て、とても感動した。
まあ、なんといっても琵琶湖は遠い。そうそう見に行けるところでもないけどな。
「電車に乗る」という手段のためだけにチョイスされた目的、日帰り比叡山。
手段のおかげで、目的にもなってなかった花火が見られてラッキーだった。
「京阪の2階建て特急に乗って、比叡山に行こう」
あの……京阪特急って、思い切り通勤特急ですが? ふつーの勤め人が通勤のために乗っている電車ですが?
それに、なんでわざわざ比叡山なの?
「比叡山に行けば、ロープウェイとケーブルカーに乗れるんだぞ」
乗れる、って……目的はソレかい。
父の旅行はいつもこうだ。
目的地は後付け。先に「なにに乗りたいから」という発想で決められる。
乗り物が先。乗り物にさえ乗ることができたら、どこにも行かずに帰ってきてもいいくらいらしい。
予定段階でモメにモメて(なんでこー、父も母もわがままで気まぐれなんだ?!)、行くのが相当嫌になったりもしたが、とりあえず比叡山に向けて日帰り旅行出発。
比叡山に行くのは何度目だろう。寺社仏閣好きの家庭に育ったために、近畿地方の主な寺には大抵行ってるからな。記憶が混ざってしまって、どこがどこやら。
しかし、こういう大きなお寺と、テーマパークと化した空間は素晴らしいね。外国の教会とかもそうだけど、信仰の場というのはとても美しい独特の宇宙がある。
根本中堂の、厨子の中で見ることはできないご本尊と、その前を照らす1200年間途絶えたことがないという不滅の法灯、そしてそれらとわたしたちを隔てる深淵。
美しいものはどこか、こわさを秘めている。
……娯楽のない時代に、この空間を作ったわけだから、すげえよな。ディズニーランドもUSJもないわけだからな。ふつーの人が苦労して山のてっぺんまで登ってきて、そこにこの空間が広がっていたら、そりゃびっくりするさ。こんな世界があったなんて!と感動するさ。はじめてのヴァーチャル・リアリティ。ひとの手によって構築された別世界を見るという経験。神も仏も、信じたくなるだろうさ。
とくに信仰を持っていないわたしでも、ははぁっ!とひれ伏したくなる空間だからな。
愉快だったのは横川の角大師だ。
わたしたち家族も、横川にまではそれまで行ったことがなかったんだ。はじめて横川に行って、清水寺に似た作りと、似てもにつかないカラーリングの横川中堂に驚嘆した、そのあと。
おみくじの元祖だとかいう元三大師堂に行ったのね。
そこにはあちこちに、とても愉快なお札が貼ってあった。
ひとめで「悪魔」だと思える姿形。
お寺に、悪魔?
それは角大師という疫神らしい。角大師の姿を写したお札を入り口に貼れば疫病封じになるし、また身につければ魔よけになるらしい。
「じつにいい味をだしている」
と、弟。デジカメにその姿をおさめながら、しみじみと言う。
ほんとに素晴らしい造形だ。角大師。ここでしかグッズが手に入らないのがまたレアだわ。わたしは角大師様の根付けを買った。だってわたし、今年厄年なんだよ。
「なんつーか、ゲームキャラみたい」
「それを見た人に『モトネタなに?』って聞かれそうだよな」
「『メガテン』とかに出てそう」
あやしくていい感じだ、角大師様。かなりお気に入り。今度また、時間のあるときにゆっくりと来よう。4時閉堂ってことで、ここにたどりついたときにはもう時間切れ、ろくに見ることができなかったのよねえ。
帰りは琵琶湖花火大会へ。
淀川花火大会がホームグラウンドなわたしたち、琵琶湖のことはなにもわかっていません。ビューポイントがどこなのか、どうすればいいのかさっぱりわからないままに、行きがけの駄賃程度の気持ちで参加。
琵琶湖花火大会は、淀川花火大会の半分の規模。だけど人出は同じ40万人。……これだけは前もって情報誌で押さえてあった。
半分の規模なのに、人出は同じ、ってなによそれ。さいてーじゃん。
淀川のものすげえ混雑ぶりを知っているだけに、辟易してたんだけど。
やっぱ田舎はいいよなっ。
大阪とは都市の作りがまったくチガウのだ。
なんなの、この道路のだだっ広さは。
淀川とちがって開放感あふれている。しかも。
その大きな道路が、完全に交通規制され歩行者天国になっているのだ。
最寄り駅から湖岸まで、歩行者天国だよ?
かなりな距離だよ?
相当な広さだよ?
「祭りとは本来、都市機能をストップさせて行うものなんだ」
と、史学科卒の弟が感慨深くつぶやく。
これだけの距離、これだけの道路をたかが「祭り」のために機能停止させるなんて。大阪ではありえない。そんなことをしたら経済に支障を来す。パニックになる。
だけど田舎では、それが可能なんだ。すごい。
都市をあげての「祭り」だ、淀川と同じ40万人が参加しているはずなのに、人混みの密度は比べモノにならない。ガラガラ。ストレス最小。湖岸へとまっすぐ伸びた大きな道路は、どこからでもよく見える。なんて楽なの、この花火見物。
打ち上げの規模は半分だとしても、演出のちがいで遜色ないモノになっていた。
淀川の花火は、縦に重ねて上がる。
琵琶湖の花火は、横に連なって上がる。
淀川では、打ち上げられる花火のあまりの数に、空が煙で白んでしまう。重ねて重ねて、同じところに打ち上げられるからだ。
琵琶湖の花火は、空間の広さを最大限に利用し、夜空全体に広がる。ひとつずつが重なることはないから、奥行きはない。
どちらがすばらしいと決めるものではないだろう。
まったくチガウふたつの花火大会を見て、とても感動した。
まあ、なんといっても琵琶湖は遠い。そうそう見に行けるところでもないけどな。
「電車に乗る」という手段のためだけにチョイスされた目的、日帰り比叡山。
手段のおかげで、目的にもなってなかった花火が見られてラッキーだった。
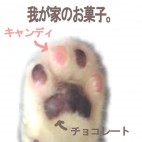
コメント