12歳。それは、「ごめん」な日々さ。@ごめん
2002年11月7日 映画 さて、今日は映画だ、『ごめん』、出演者舞台挨拶付き試写会。
試写会だから行った。自分で金を払うなら絶対行っていない。
とゆーのはべつに、映画のできばえ云々でなく、この映画の予告を見たときに思ったこと。
わたしはきっと、この映画では楽しめないだろう。そう思ったからだ。
実際見に行って……まあ、まがりなりにも映画だから、ちゃんとたのしんだけれど、やっぱり感想は変わらなかった。
金を出してまで見たくない。
予告を見て思ったとおり、わたしはこの映画には向かない。たのしめない。
では、どんな人が楽しめるのだろう?
児童文学の映画化作品、らしい。主人公は小学6年生の男の子。彼はクラスで(たぶん)いちばんに「蛇口が開いた」(映画の中での表現のひとつ。他には「汁が出た」とか)。そして彼は、ふたつ年上の中学2年生の女の子に恋をする。初恋ってやつだ。
つまり、カラダもココロも思春期なわけだ。
そんな男の子の日常の物語。
「ほほえましくもちょっと切ない、誰もが経験する思春期の一瞬を切り取った宝箱のような映画です」
と、もらったチラシには書いてあった。
そしてわたしは、映画を見ている間中、首を傾げていた。
この映画、視聴対象者は、誰を想定しているんだろう??
チラシのあおりを見る限り、大人が対象のようだ。今の子どもの青い初恋を見ることによって、昔の自分を思い出してほろ苦い気持ちになれってか。
たしかに、そんなふーな作りもしてあった。
というのも、笑いが起こる場面というのが、スクリーンの子どもたちが「大人のような言動」を取るシーンばかりなのな。
恋愛関係で、大人の男と女がかわすような言葉を、神妙な顔で子どもが言う。ソレを見て大人である観客が笑う。
……てことはこれ、大人対象?
しかし、大人対象であり、「ほほえましくもちょっと切ない、誰もが経験する思春期の一瞬を切り取った宝箱のような映画」とするにはあまりにも、ファンタジーが欠けている。
せつなさや痛み、うつくしさ。はかなさや、きらめき。
大人が失った時代を懐古して、掌の中の宝物をのぞくような気持ちにはほど遠いんだけど、この映画。
「今の子どもをリアルに描いているから、ファンタジーに欠けるのは仕方ない」……という意味でもない。現在をリアルに描いたって、ファンタジーを描くことはできるからだ。
なんだかとても、中途半端だったんだ。
たとえばこの映画を子どもが見て、たのしめるのか?
あまりにもファンタジーに欠けるので、大人対象だとは思えなかった。では、実際に今現在、登場人物と同じ年代の子どもたちが見て、共感できるのか?
わたしには、それが疑問だった。
現在の子どもから見れば、「なんだこれ。ズレまくってる」「こんな子どもいないよー(失笑)」なものじゃないのか? と。
わたしは原作を読んでいない。だから、原作がどうなのかはわからない。
しかし、原作は「子どものモノ」に近いスタンスなんじゃないだろうか。
子どもが読んで共感できる作品なんじゃなかろーか。
しかし、映画は大人のモノだ。大人が見るためにつくられている。
わたしが感じた「気持ち悪さ」はそこに由来しているのではないだろうか。
現在の子どもが共感できる物語を、「大人の目線」で撮っていること。
大人が、「子どもってのはこんなもんだよな」と、見下して作っている。
高いところから、見おろしている。
だから、主役の子どもが大人びた物言いをするシーンで、大人の観客が笑う、などという状態になる。
なんで笑う? 子どもからしたらその言葉は「大人の真似」ではなく、ナチュラルに今現在使っている言葉なんじゃないの? 勝手に大人が「意味もわからず、大人の真似をして。ふふっ、子どもね(笑)」と思っているだけじゃないの?
全編に気持ち悪さが漂っていて、素直に「ほほえましくもちょっと切ない、誰もが経験する思春期の一瞬を切り取った宝箱のような映画」としてたのしめなかったのよ。
わたしが子どもの恋を描くなら、こんな描き方はしたくない。
大人向けにノスタルジックにやる。わたしにはもう、リアルな現在の子どもなんか描けないから。それくらいなら、現代のエッセンスを使いながらも「完全に大人向け」な作品にする。
こーゆー気持ち悪い思い上がった作品は、描きたくないよぅ。
かえって原作に興味がわきました。原作はすごくおもしろいのかも。
「父親」の存在はすごくよかった。主人公の父親も、ヒロインの父親も。どっちもタイプはちがうが、かわいい大人の男たち。
んで、出演者たちの舞台挨拶。
……子どもはいいよな。ふつーに喋るだけでもウケる。ってソレ、動物扱いされてるよーなもんだけどな。
クールでモテモテの少年(ひとりだけいつも短パン。……サービス? 彼がお花ちゃんなの?)役の子が、「役柄が正反対すぎて苦労しました」と言っていたのが印象的。いちばん小柄で幼い子。だけどものすごく大人びた喋り方。照れてろくに喋れないんだけど……言葉の端々に「うわ、この子すげー大人っぽい」というのが匂っていた。
主役の子が「演技というか……ほとんど地というか……もごもご」と、姿勢も悪く、素人同然のぱっとしない喋り方で通していたのもまた、印象的。
そして主役の子は言う。「なんで『ごめん』ってタイトルなのかわかりません……台詞でも2回くらいしか出てこないし……」
そっか、わかんないのか。
わたしにはわかったけどなあ。
主人公たちが剣道部ってのも、タイトルにひっかけてあるんだろーなー、と思って最初にくすりとしたけどな。
☆
見終わった後、隣の席のカップルが席を立ちながら喋っていた。
女「わたしのオバが出てたから、おどろいちゃった(首を傾げている。どーやら知らなかったらしい)」
男「オバさん? えっ、出てたの?!」
女「うん、ちらっとだけど。オバさん、元宝塚だから……。テレビでも、サスペンス劇場の犯人の母親とかしか、やってないし……」
なんですとぉ?
出てたのか、元タカラジェンヌ?! 誰だよ?
わかるわけないけどな……そっか……サスペンス劇場の犯人の母親か……せつないなー。
試写会だから行った。自分で金を払うなら絶対行っていない。
とゆーのはべつに、映画のできばえ云々でなく、この映画の予告を見たときに思ったこと。
わたしはきっと、この映画では楽しめないだろう。そう思ったからだ。
実際見に行って……まあ、まがりなりにも映画だから、ちゃんとたのしんだけれど、やっぱり感想は変わらなかった。
金を出してまで見たくない。
予告を見て思ったとおり、わたしはこの映画には向かない。たのしめない。
では、どんな人が楽しめるのだろう?
児童文学の映画化作品、らしい。主人公は小学6年生の男の子。彼はクラスで(たぶん)いちばんに「蛇口が開いた」(映画の中での表現のひとつ。他には「汁が出た」とか)。そして彼は、ふたつ年上の中学2年生の女の子に恋をする。初恋ってやつだ。
つまり、カラダもココロも思春期なわけだ。
そんな男の子の日常の物語。
「ほほえましくもちょっと切ない、誰もが経験する思春期の一瞬を切り取った宝箱のような映画です」
と、もらったチラシには書いてあった。
そしてわたしは、映画を見ている間中、首を傾げていた。
この映画、視聴対象者は、誰を想定しているんだろう??
チラシのあおりを見る限り、大人が対象のようだ。今の子どもの青い初恋を見ることによって、昔の自分を思い出してほろ苦い気持ちになれってか。
たしかに、そんなふーな作りもしてあった。
というのも、笑いが起こる場面というのが、スクリーンの子どもたちが「大人のような言動」を取るシーンばかりなのな。
恋愛関係で、大人の男と女がかわすような言葉を、神妙な顔で子どもが言う。ソレを見て大人である観客が笑う。
……てことはこれ、大人対象?
しかし、大人対象であり、「ほほえましくもちょっと切ない、誰もが経験する思春期の一瞬を切り取った宝箱のような映画」とするにはあまりにも、ファンタジーが欠けている。
せつなさや痛み、うつくしさ。はかなさや、きらめき。
大人が失った時代を懐古して、掌の中の宝物をのぞくような気持ちにはほど遠いんだけど、この映画。
「今の子どもをリアルに描いているから、ファンタジーに欠けるのは仕方ない」……という意味でもない。現在をリアルに描いたって、ファンタジーを描くことはできるからだ。
なんだかとても、中途半端だったんだ。
たとえばこの映画を子どもが見て、たのしめるのか?
あまりにもファンタジーに欠けるので、大人対象だとは思えなかった。では、実際に今現在、登場人物と同じ年代の子どもたちが見て、共感できるのか?
わたしには、それが疑問だった。
現在の子どもから見れば、「なんだこれ。ズレまくってる」「こんな子どもいないよー(失笑)」なものじゃないのか? と。
わたしは原作を読んでいない。だから、原作がどうなのかはわからない。
しかし、原作は「子どものモノ」に近いスタンスなんじゃないだろうか。
子どもが読んで共感できる作品なんじゃなかろーか。
しかし、映画は大人のモノだ。大人が見るためにつくられている。
わたしが感じた「気持ち悪さ」はそこに由来しているのではないだろうか。
現在の子どもが共感できる物語を、「大人の目線」で撮っていること。
大人が、「子どもってのはこんなもんだよな」と、見下して作っている。
高いところから、見おろしている。
だから、主役の子どもが大人びた物言いをするシーンで、大人の観客が笑う、などという状態になる。
なんで笑う? 子どもからしたらその言葉は「大人の真似」ではなく、ナチュラルに今現在使っている言葉なんじゃないの? 勝手に大人が「意味もわからず、大人の真似をして。ふふっ、子どもね(笑)」と思っているだけじゃないの?
全編に気持ち悪さが漂っていて、素直に「ほほえましくもちょっと切ない、誰もが経験する思春期の一瞬を切り取った宝箱のような映画」としてたのしめなかったのよ。
わたしが子どもの恋を描くなら、こんな描き方はしたくない。
大人向けにノスタルジックにやる。わたしにはもう、リアルな現在の子どもなんか描けないから。それくらいなら、現代のエッセンスを使いながらも「完全に大人向け」な作品にする。
こーゆー気持ち悪い思い上がった作品は、描きたくないよぅ。
かえって原作に興味がわきました。原作はすごくおもしろいのかも。
「父親」の存在はすごくよかった。主人公の父親も、ヒロインの父親も。どっちもタイプはちがうが、かわいい大人の男たち。
んで、出演者たちの舞台挨拶。
……子どもはいいよな。ふつーに喋るだけでもウケる。ってソレ、動物扱いされてるよーなもんだけどな。
クールでモテモテの少年(ひとりだけいつも短パン。……サービス? 彼がお花ちゃんなの?)役の子が、「役柄が正反対すぎて苦労しました」と言っていたのが印象的。いちばん小柄で幼い子。だけどものすごく大人びた喋り方。照れてろくに喋れないんだけど……言葉の端々に「うわ、この子すげー大人っぽい」というのが匂っていた。
主役の子が「演技というか……ほとんど地というか……もごもご」と、姿勢も悪く、素人同然のぱっとしない喋り方で通していたのもまた、印象的。
そして主役の子は言う。「なんで『ごめん』ってタイトルなのかわかりません……台詞でも2回くらいしか出てこないし……」
そっか、わかんないのか。
わたしにはわかったけどなあ。
主人公たちが剣道部ってのも、タイトルにひっかけてあるんだろーなー、と思って最初にくすりとしたけどな。
☆
見終わった後、隣の席のカップルが席を立ちながら喋っていた。
女「わたしのオバが出てたから、おどろいちゃった(首を傾げている。どーやら知らなかったらしい)」
男「オバさん? えっ、出てたの?!」
女「うん、ちらっとだけど。オバさん、元宝塚だから……。テレビでも、サスペンス劇場の犯人の母親とかしか、やってないし……」
なんですとぉ?
出てたのか、元タカラジェンヌ?! 誰だよ?
わかるわけないけどな……そっか……サスペンス劇場の犯人の母親か……せつないなー。
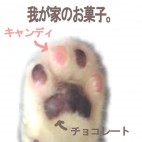
コメント